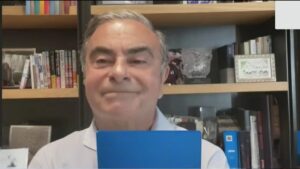F-35 Lightning II
欧州が米国に依存する主要な防衛分野
ドナルド・トランプ氏の米国大統領復帰による外交政策の転換は、ヨーロッパの防衛産業界および軍関係者に大きな衝撃を与えています。
米軍のヨーロッパからの撤退の可能性(2万人の兵力削減、ウクライナ戦争前の水準への回帰)に加え、ワシントンのモスクワへの傾斜が、ヨーロッパ各国に依存度を見直す動きを促しています。
欧州で米国からの武器輸入が増加した理由
ストックホルム国際平和研究所によると、2014年から2018年の間、ヨーロッパ大陸の武器輸入の35%が米国からのものでしたが、2014年から2018年の間には55%以上に増加しました。
米国製兵器の輸入の増加は以下の理由によるものです。
- ウクライナ戦争における協力協定の更新と新規契約:
ウクライナ戦争を契機に、ヨーロッパ各国は米国との間で多数の兵器に関する契約や協力協定を更新、あるいは新たに締結しました。これにより、以前から存在していた依存関係がさらに強化され、米国からの兵器輸入が増加しました。 - 米国の支援メカニズム:
米国の強力な購入・融資メカニズムである対外軍事販売(Foreign Military Sales)と対外軍事資金援助(Foreign Military Financing)が、長年にわたり兵器の輸出を支援しており、ヨーロッパ諸国もこれを利用したためです。特に、ポーランド、ルーマニア、ブルガリア、スロバキア、チェコ、バルト三国などがこれらのメカニズムの主要な受益国となっています。 - 需要の高まり:
ウクライナでの戦闘を経て、米国の長距離砲兵システムであるHimarsなどの兵器に対する需要がヨーロッパで高まりましたが、ヨーロッパには独自の解決策が不足していたことも輸入増加の要因と考えられます。
ドナルド・トランプ氏のホワイトハウス復帰以来の米国の外交政策の転換が、ヨーロッパの防衛産業界に影響を与え、依存を制限する検討が始まった背景があるものの、現状としては米国製兵器への依存は増している状況です。
欧州27カ国中13カ国がロッキード・マーティン製の戦闘機F-35に依存
ロッキード・マーティン製のこのステルス機は最高の性能を誇りますが、その操縦は米国にある特定のセンターに保存されている非常に多くの戦術データの融合に依存しています。
メンテナンスも同様で、一部は自動化されたソフトウェアに関連しています。
元戦闘機パイロットでフランス国際関係研究所の准研究員であるジャン=クリストフ・ノエル氏は、「アメリカ人は水道の蛇口を握っているようなもので、直接関わっていなくても、多かれ少なかれ開閉の調節ができる」と述べています。
また、ロッキード・マーティンと多くの専門家によると、いわゆる「キルスイッチ(停止ボタン)」は存在せず、航空機を完全に停止させることはできません。
3月12日にパリの陸軍士官学校で開催された防衛フォーラムにおいて、オランダのルーベン・ブレケルマンス国防大臣も同様の見解を示しました。同氏は、「F-35プログラムの運用可能な状態を維持することは、各国にとっての緊急事項である。」と強調しました。
輸送機及び空中給油機
長年、ヨーロッパは輸送機と空中給油機も大幅に不足しています。北大西洋条約機構(NATO)内では、これらの任務は主にアメリカ軍によって遂行されています。戦略国際問題研究所のデータによると、2023年の時点で、ヨーロッパの空中給油機は150機であったのに対し、米国は450機以上を保有しており、輸送機A400Mはヨーロッパが145機、ワシントンが232機を保有していました。
ヨーロッパは偵察機も依然として不足しており、米国の125機に対し、わずか35機しかありません。英国のシンクタンクである国際戦略研究所のブログに3月3日に掲載されたノートで、ダグラス・バリー氏は、「独立追求は、大規模な投資がなければ達成困難な課題となるだろう」と警告しています。
宇宙分野における弱点
米国の転換により、ブリュッセルにおけるヨーロッパの主権に関する議論も再検討される可能性があります。
特にトランプ氏の選挙前から開始されていた、必要な場合には米国の兵器も含め、共同で武器を購入することによって、重大と見なされる能力のギャップを迅速に埋めることを目的とした産業イニシアチブを通じてです。
2024年末、この主権を熱心に推進するフランスは、いまだに停滞している「EDIP」と呼ばれる計画の枠組みの中でドイツと対立しました。ドイツ政府は、自国領土での米国製パトリオットミサイルのライセンス生産に対して欧州の資金援助を得ようとしており、これがフランス政府の怒りを買いました。
米国の衛星への依存
ヨーロッパは、ミサイル発射を探知するためのレーダー群である極めて機密性の高い「早期警戒」分野においても、米国との戦略的利益の分離のリスクに強く懸念を抱いています。この広大な構造、いわゆるイージスシステムは、地中海、大西洋、バルト海を航行できるレーダーを装備した米軍艦艇(近年、ヨーロッパ海域から離れる傾向がありましたが)と、トルコ、ルーマニア、ポーランドにある3つの軍事基地(米軍がNATOの管理下で運用)に依存しています。
イージスシステムのレーダーが機能するためには、米国の衛星が必要です。それらがミサイルの軌道を予測することを可能にします。この意味で、「早期警戒」の課題は、宇宙部門におけるヨーロッパの主要な弱点を明らかにしています。
フランス側では、この問題は非常に真剣に受け止められており、国家元首が6月までに要求する新たな宇宙戦略に組み込まれる予定です。しかし、この分野への投資には巨額の資金と時間が必要です。その一方で、米国は軍事的なアプローチを大きく変えようとしています。
幻想的な自律性
欧州軍は、ウクライナでの戦闘において使用頻度の高い兵器、例えば米国の長距離砲兵システム「HIMARS」のようなものに関しても、独自の解決策を持っていません。デジタル、電気通信、サイバー、インテリジェンスにおける完全な自律性はまだ幻想と言えます。欧州軍が余地を取り戻し始めたのは砲弾の分野だけであり、EUが支援する大規模な投資によるものです。
グロス氏は、「ヨーロッパは現在、アメリカ人よりも多くの砲弾を生産している」と断言しています。同氏は、「現在のアメリカの兵器庫の生産量はヨーロッパよりも少なく、ウクライナ軍は米国が提供した広大な備蓄のかなりの部分を使い果たしてしまっていたが、これまでウクライナ軍が持ちこたえてこられたのは、生産性が高いヨーロッパの砲弾が備蓄を支えてきたからだ。」と付け加え、ドイツの巨大企業ラインメタルによる重要な貢献を強調しています。
しかし、ヨーロッパの戦争努力の持続可能性は、砲弾の生産性を維持したまま、兵器の生産性を上げられるかどうかによります。
FRSの研究員であるエレーヌ・マッソン氏は、3月初旬に発表されたノートの中で、米国が「短期間に十分な数のHIMARSシステムやエイブラムス戦車を供給するのに苦労した」ため、例えばポーランドは2022年に一部の装備について韓国に目を向けたことを指摘しています。
マッソン氏は、「安全保障上の保証は今後、同盟国にとってより高い代償を伴うことになり、アメリカ製の兵器システムを優先的に運用することを強いられる可能性がある」と付け加えています。
アメリカの世界戦略において、中国の封じ込めは、部分的には「国際的な生産チェーンにより多くのパートナーや同盟国を関与させる」ことによって実現されるとされており、欧州の中でトランプ氏の政策に最も同調している国であるイタリアのグイド・クロセット国防大臣は3月12日にパリで、「産業自律の名の下に西側同盟を崩壊させてはならない」と主張しています。
ヨーロッパ再軍備計画
アメリカ大統領選挙後、「E5」と呼ばれる非公式グループ(ポーランド、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア)の国防大臣がパリで会合を開きました。
この会合の主な目的は、アメリカの政策転換、特にドナルド・トランプ氏の再選によって起こりうる影響について議論し、対応を検討することで、ドイツのボリス・ピストリウス国防大臣は、2月中旬にピート・ヘグセス米国防長官に対し、この問題に関する「ロードマップ」を提案したと述べました。
具体的には、以下の点に焦点が当てられました。
- 新たな「負担の共有」の組織化:
アメリカが求めるであろう新たな防衛負担の分担について、どのように対応していくかを検討しました。ドイツのボリス・ピストリウス国防大臣は、2月中旬からアメリカの国防長官ピート・ヘグゼセス氏に対して、この件に関する「ロードマップ」を提案していたことを明らかにしました。 - 能力の空白(キャパシティギャップ)の回避:
アメリカの関与が低下した場合に生じうる防衛能力の不足を防ぐための対策を協議しました。 - 段階的な移行の実現:
アメリカとの間で、それぞれの役割を明確にし、損失を補填するための段階的な移行計画を策定することを目指しました。 - 欧州の自主性強化の動き:
3月4日に欧州委員会によって発表された、新たな市場投資のために最大1500億ユーロを調達することを目標とし、ヨーロッパ再軍備計画の実行資金に充てます。
この会合は、アメリカの外交政策の不確実性に対するヨーロッパ側の危機感と、防衛における自主性を高める必要性の高まりを背景として開催されたと言えます。会合の結果、具体的な共同声明などが発表されたわけではありませんが、ヨーロッパ主要国がアメリカの動向を注視し、自主的な防衛体制の構築に向けて連携を模索していることが示唆されています。
自律化に向けた準備
アメリカからの自律化の動きを始めるとしても、まず兵器以外の分野、特に支援に関わるすべての分野から始める必要性があります。
戦略研究財団(FRS)の研究員で米国専門家のフィリップ・グロス氏は、「兵器システムほど目立たないものの、修正すべき喫緊の課題は各種の支援システムである。」と指摘しています。
この問題は、兵站、メンテナンスだけでなく、医療支援や任務装備(センサー、レーダーなど)にも同様に関わっており、これらは欧州軍がごくわずかしか備えていない分野です。
米国政策の変化が欧州防衛産業にもたらす影響
米国政策の変化は、欧州の防衛産業に複数の重要な影響をもたらしています。
まず、ドナルド・トランプ氏のホワイトハウス復帰以来の米国外交政策の転換は、ヨーロッパの軍幹部や防衛産業界全体に大きな衝撃を与えています。「地殻変動」とも形容されるこの変化は、ヨーロッパ諸国に米国への依存を減らすための新たな検討を促しました。
具体的には、以下のような影響が挙げられます。
- 米国軍兵力の削減への懸念:
一部の米国防総省当局者が示唆する2万人の米軍部隊のヨーロッパからの撤退は、ウクライナ開戦前の水準への回帰を意味し、ヨーロッパの安全保障体制における潜在的な空白を生み出す可能性があります。 - 米国の対モスクワ傾斜への懸念:
ワシントンがモスクワの利益により一層傾倒するのではないかという懸念が、ヨーロッパ各国の首都で、米国への依存を制限するための前例のない検討を引き起こしました。 - 新たな「負担の分担」への対応:
米国が求める新たな負担の分担に対応するため、ドイツのボリス・ピストリウス国防相は、2月中旬から米国防長官に対し、この問題に関する「ロードマップ」を提案しました。この文書は、各国の間で戦力のギャップを生じさせることなく、誰が何を行い、どのように損失を補填するかという段階的な移行を組織化することを目的としています。 - 欧州の自主性強化の動き:
米国の政策変化を受け、「ヨーロッパ再軍備」計画が欧州委員会によって3月4日に発表されました。この計画は、市場からの新たな投資のために最大1500億ユーロを調達することを目標としており、米国への依存を減らすという点で共通の精神を持っています。 - 支援分野における自主性の必要性:
兵器システムそのものよりも目立たないものの、ロジスティクス、メンテナンス、医療支援、センサーなどのミッション装備といった支援分野における米国への依存を早急に是正する必要性が指摘されています。 - 宇宙分野における脆弱性:
早期警戒システム「イージス」の運用が米国の衛星に依存している現状は、ヨーロッパの宇宙分野における重大な弱点を示しており、戦略的利益の乖離に対する懸念を引き起こしています。フランスはこれを深刻に捉え、新たな宇宙戦略に盛り込む予定ですが、多額の投資と時間が必要とされています。 - 欧州の防衛主権を巡る議論の再燃:
米国の政策転換により、ブリュッセルではヨーロッパの主権に関する議論が再検討される可能性があります。これには、米国製兵器の共同購入を含む、能力ギャップを迅速に埋めることを目的とした産業イニシアチブが含まれます。しかし、ドイツが米国製パトリオットミサイルのライセンス生産に欧州の資金援助を求めた件では、フランスとの間で意見の衝突も見られました。 - 安全保障のコスト上昇と米国製兵器の優先:
米国の安全保障の保証は同盟国にとってより高価になる可能性がありますが、米国製兵器システムの優先的な運用を強いられる可能性も指摘されています。米国のグローバル戦略において、中国の封じ込めは、同盟国を国際的な生産チェーンにより深く関与させることを一部としているため、このような状況が生じうるとしています。
米国政策の変化は、ヨーロッパの防衛産業に対し、米国への依存という課題を改めて認識させ、自主防衛能力の強化に向けた動きを加速させる一方で、技術的な制約や国家間の利害の対立といった多くの課題も突き付けています。