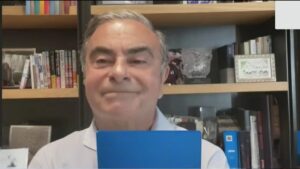米国の保護からの転換期
「祖国はあなたとあなたの献身を必要としています」と、フランスのエマニュエル・マクロン大統領は3月5日20時からの演説で、1500万人のテレビ視聴者が見守るフランス国民への演説で述べました。
ウクライナ戦争と地政学的な脅威のみについて行われたこの14分間の演説は、「ロシアの脅威」、「危険な世界」、「時代の変化」などについて説明し、国民の協力を仰ぐものでした。
演説の視聴率は71.6%と高く、テレビの前にいなかった若者たちもソーシャルネットワーク上で演説を追っており、若者を含む国民の殆どがこの演説が意味することを理解したと言えるでしょう。
今後数年以内に戦争が起こりうると考えるフランスの若者たち
CNRS(フランス国立科学研究センター)の研究ディレクターであるアンヌ・ミュクセル氏が指揮した調査「若者と戦争、その表象と関与の傾向」によると、若者の大多数は今後数年間に戦争が起こる可能性があると考えており、そのほぼ半数がフランス国内で戦争が起こる可能性があると考えていると言います。
若さはもはや軽快さを象徴する言葉ではなく、新型コロナウイルス感染症のパンデミック、地球温暖化、そして今や世界的紛争の恐怖に圧迫され、不確実さと重苦しさをイメージさせる言葉に変わりつつあります。
Le Parisien紙では、マクロン大統領の演説の翌日に、街頭の若者たちのインタビュー記事を載せています。
フランスの若者たちの反応
24歳のギョームの場合
「フランスが戦争状態にあると初めて聞いたのは、2015年のテロ攻撃の後でした。」と、当時大統領だったフランソワ・オランド氏の発言を引用して、ヴァンデ在住の24歳の整備士であるギョームは回想します。
「当時僕はその言葉を抽象的な話だと捉えながら聞いていましたが、今は違います。フランス中の何百万人もの若者と同様に、戦争はもはや備えるべき可能性となり、日々近づきつつあることを実感しています。」
「僕たちは派兵から免れることができるのでしょうか?僕たちとウクライナやロシアの若者では何が違うのでしょう?彼らもある日ロシアの侵攻が始まるまで、自分たちが実際に徴兵されるとは考えていなかったはずです。僕たちにも”その日”が近づいてきている気がするのです。」
彼は時々、どこか他の地へ行きたいと思うことがあります。もっと穏やかな場所へ。
「オーストラリアがいいかもしれません。」と彼は真剣にフランスからの脱出を考え始めています。
25歳のレアの場合
5月からベルギーで広報担当の職に就く予定のレアにとって、フランスから脱出することは数年前から計画されていました。「私の友人たちは、フランスの日常から逃れて海外で働く人が殆どです。」と、25歳の彼女は言います。
「ベルギーに移ってもEUの圏内にいることには変わりません、それでもフランスを離れることにより少しでも戦争から距離をおける気がするのです。」
レアは、戦争に向かおうとする国際情勢が人々に引き起こす心理的な影響を強調しています。「私たちのほとんどは精神的なセラピーを受けており、将来への恐怖が、子供を持ちたくないという願望として現れています。カップルであっても子どものいる家庭を夢見る人は周りに誰もいません。私も30歳になる時に決断しようと思っていますが、今は将来に対する希望も展望も何も描くことができません。
18歳のオードリーの場合
「特に米国でトランプ大統領が当選して以来、フランス国内で戦争が起こる可能性について考えずにはいられません。」とパリ・シテ大学(VI)の法学部生、オードリーさん(18歳)は言います。「このテーマが大学で大きな話題になっており、学生同士でこのことについて話すとき、不安と否定の間で感情が揺れ動きます。欧州連合は抵抗するための国境だと信じている人がまだたくさんいます。私もそう願っています。そういう意味では、欧州の首脳陣が団結したロンドンサミットの映像は、私に少し安心感を与えました。でもそれがいつまで続くのか?という問いに答えられる人が誰もいないのです。」
25歳のウェンの場合
恵まれない学生を支援するCOP協会のディレクターであるウェンは、「ウクライナの侵攻以来、フランスが武力紛争に参加する可能性は、学生の間で定期的に会話に上るようになっていましたが、トランプとゼレンスキーの衝突があってからは、毎日がこの話題で持ち切りです。私が出会う若者たちは皆唖然とし、学業を続けていけるのか、その後はどうなるのか、不安な気持ちを訴えてきます。第三次世界大戦に対する学生たちの不安の高まりを少しでも和らげることができる情報を求めてニュースを探すことが日常になり、一種の地政学の専門家になったような気がします。
19歳のソハムの場合
「衝動のままに行動する個人に翻弄される世界に生きていることに、日々不安を感じています。」と、ナンテール大学の1年生で人文科学、法律、経済経営を専攻する19歳のソハムは声を詰まらます。今や「核の脅威」、「前線」、「政治の二極化」といった言葉は日常会話の中心となっており、「合理性がもはや存在しない世界で、いつか自分も軍事的な現場に行くかもしれないという考えに支配され、パリが爆撃される悪夢を見るほどです。」
「これらの不安は10月7日のイスラエル・パレスチナ紛争から強くなり、ウクライナの情勢、トランプ大統領の発言、ドイツの極右の台頭など…毎日ニュースを読むたびに、パニックに陥りそうになるので、読むのは週に一度にしています。
以前は、この国で紛争が起こった場合には核の抑止力が武器となり、冷戦のような状態が続くのではないかと思っていました。しかし今では、冷戦の時期はすでに過ぎ去ってしまったのではないかという気がしています。」
20歳のジュスティーヌの場合
ストラスブール政治学院の3年生であるジュスティーヌは、「武器を持って戦う必要があるならば、私には参戦する準備ができています。軍人としてのキャリアを考えているからかもしれません。」と迷わずに答えます。「私は予備役であり、いつか軍事的な現場に行く可能性があることをよく理解しています。法的権限を持たない国際機関が紛争を回避するには限界があるでしょう。私たちは帝国主義的なロシアと、その限界がよくわからない堕落した人物に翻弄されているのです。」と、彼女はプーチン大統領を容赦なく指して言います。
第三次世界大戦の可能性の中で生きる「戦争を知らない子どもたち」
2001年、世界最強の国がアルカイダによって攻撃され、その経済的および政治的勢力の象徴であったNYのワールドトレードセンターが破壊されました。その頃に欧州で生まれた子どもたちが20代になり、今はウクライナと自分たちの国を守るために武器を取る必要があるのかと自問しています。
彼らは、新型コロナ、気候変動、紛争の脅威と、不確実性に満ちた青春時代を過ごし、第三次世界大戦の可能性が高まる中で大人になり、これからの国を背負っていく立場となりました。争いは暴力に限らず、経済的、政治的、イデオロギー的と、どのような形で攻撃されるかはわからず、全てのことに疑心暗鬼になっています。
テロの脅威と戦争の恐怖
テロはすべての大陸に打撃を与え、特にフランスは大きな被害を受けました。
まず最初に2012年のトゥールーズ、次に2015年のパリ、2016年のニースなど、多くの都市に致命的な傷を残しました。この脅威が(少し)収まってきたかと安心したのもつかの間、3年前からはウクライナでの戦争が新たな恐怖を浮き彫りにしました。
新たな恐怖とは、第二次世界大戦と共に消滅したと思われていた塹壕戦争、強制的な徴兵、前線に残されたままの死者、爆撃を避けて地下壕で生活する人々、もはや映画の中にしか存在しないと思われていた古めかしい戦争が、ドローンなどの新たな技術を装備して過去から蘇ったのです。
そしてドナルド・トランプ大統領の就任とともに書き換えられた新たな国際同盟によって、軍靴の音が欧州に響き始めています。
現在の若者たちの親世代は、ベルリンの壁の崩壊やEUの創設など、自由と協調に向かう新たな時代の中で、永遠に平和が続くかのような、戦争の不安がない時代を享受してきましたが、自らの子供たちはその恩恵を受けられず、祖父母たちより前の時代に引き戻されるなどと、誰が想像できたでしょうか。
ヨーロッパ諸国における軍事徴兵の再開
ヨーロッパ諸国は、変化する安全保障環境に対応するために、軍事徴兵の再開をする国が増えており、特にロシアに距離的に近い国々に、若者の徴兵を義務化する国が増えています。
再導入国:
- リトアニアは2015年に徴兵制を再導入しました。
- スウェーデンは2017年に徴兵制を再導入しました。ちなみにスウェーデンでは、男女ともに兵役が義務付けられています。
- ラトビアは2023年に徴兵制を再導入しました。
再導入検討国:
- ドイツでは、2025年にも兵役義務が再開される可能性があります。
- ベルギーも2026年に兵役義務の再開を検討しています。
既存の徴兵制:
ノルウェー、フィンランド、エストニア、スイス、オーストリア、デンマーク、ギリシャ、キプロスは、すでに徴兵制を導入しています。
徴兵の形態:
- スウェーデンでは、18歳の男女全員に質問票が送られ、軍が採用できる人物を評価します。2017年には、11万人の中から約8500人が選ばれました。
- デンマークでは、一部の世代のみが対象となり、適格と判断された男性は4〜12か月の任務に志願できます。
- ギリシャでは、19歳から45歳までの男性が原則として軍隊で兵役を行う必要があります。
- スイスでは、兵役を自主的に拒否する人は、代替として社会奉仕を行うことができます。
新しい徴兵の形:
徴兵制を再開する国々は、「冷戦時代の軍隊に戻るつもりはない」としており、女性の参加を促し、より柔軟なモデルを検討しています。
現代の戦闘に求められるスキル:
ヨーロッパの軍隊は、特定のスキルと能力を持つ多様な人材を求めています。特に、技術的な専門知識を持つ人材の需要が高まっています。
- フランス軍:宇宙、量子、サイバー、ドローン、人工知能などの分野で人材を求めています。2025年には、これらの分野を中心に27,000以上のポストを募集する予定です。
- ドイツ軍:軍隊の規模拡大を目指しており、2025年には徴兵制を再開し、より多くの兵力を確保しようとしています。スウェーデンのように、コンクリートの能力に応じて選抜する可能性があります。
- スウェーデン軍:18歳の男女全員にアンケートを送り、軍が採用できる人材を評価し、能力に応じて選抜します。特に、ドローンの操縦士など、特定のスキルを持つ人材を求めています。
フランスにおける兵役義務
フランスは、フランス革命以来、国民皆兵の思想に基づいた徴兵制を敷いていました。
しかし、20世紀後半以降、冷戦の終結や軍事技術の高度化などを背景に、徴兵制の見直しが進みました。
歴史的背景:
- 1997年、当時のジャック・シラク大統領が徴兵制の停止を発表し、2001年に正式に廃止されました。
- 1998年、当時のジャック・シラク大統領が国家奉仕制度改革の一環として、国防・市民の日(Journée Défense et Citoyenneté)を制定しました。これは、1997年に停止された兵役に取って代わったものです。
- 2001年以降、徴兵制は停止され、職業軍人制に移行しました。
- 2018年、マクロン大統領は、16歳の男女を対象とした「国民奉仕活動(SNU)」を導入しました。
現在の状況:
- 現在、フランスでは徴兵制は廃止されていますが、国民は16歳になったら「国民奉仕活動(SNU)」を受けることができ、18歳になったらJDC(防衛と市民の日)を受ける必要があります。
- 国民奉仕活動(SNU):
- 16歳の男女を対象とした1か月間のプログラムで、国防意識の向上、社会奉仕活動、市民教育などを目的としていますが、SNUは義務ではありません。
- SNUは、2段階に分かれており、第一段階は、集団生活を通して、規律や連帯感を養うことを目的としています。第二段階は、社会奉仕活動を通して社会貢献を目的としています。
- 国防・市民の日(Journée défense et citoyenneté (JDC)):
- フランス国内または海外に居住するフランス国籍を持つ男女全員に義務付けられており、16歳から25歳までの若者を対象としています。
- 市民権、記憶の義務、防衛、軍隊、国家、ヨーロッパの問題に対する認識を
扱う 1 日プログラムです。
- フランス軍は職業軍人のみで構成されていますが、予備役制度も存在します。
フランスでは、かつての徴兵制は停止され、現在は国民奉仕活動(SNU)と国防・市民の日(JDC)という制度が導入されています。これらの制度は、国防意識の向上や社会貢献を目的としており、国民の国防に対する意識を高めることを目指しています。
ヨーロッパの殆どの国では、既に徴兵制度を採用していますが、若者全員に対する義務とする国と、職業軍人として募集をして希望者だけを採用する国に分かれます。その大きな違いは、兵役期間の報酬が支払われるかどうかにあり、職業軍人の増加に伴い国家予算も肥大します。
徴兵制には人権上の問題や、経済的な負担などの課題も指摘されており、現在フランスは希望者だけを職業軍人として採用し、報酬が支払われています。しかしEUで唯一の核保有国であり、欧州のリーダーシップを取ろうとするフランスの若者に徴兵義務がないのは無理があるとし、徴兵制復活を求める声が高まっています。
徴兵制復活を求める声は65歳以上の人々が最も多く、次に50歳以上(兵役義務は経験したが戦地には行ったことがない世代)、当然ながら30代以下の賛成が最も少ないことが、兵役に行って欲しいけれども、自分は行きたくない(自分の子どもも兵役年齢を過ぎている)という人々の本音を表しているようです。
フランスはNATOに加盟しているため、戦争が始まったら自国を守るだけでなく、戦地に派兵される可能性も高くなります。
兵役時代の思い出を美化して語る世代ではなく、実際に戦争に行かされる若い人たちの声こそが重要なのではないのでしょうか?

『戦争とは、爺さんが始めて、おっさんが命令し、若者たちが死んでいくもの』と昔言っていたのは大橋巨泉だったけど、今も状況は何も変わっていないことに驚く。もしも、高齢でもどんな職業でも、戦争を始めることに賛成した人たちが前線で戦うこと、という法律ができたら、それでも政治家や権力者たちは戦争を始めるのだろうか?(今やモービルスーツを装着できる時代だから、体力がないということは言い訳にはならないよ。)
フランスの若者たちは、徴兵制度がまた義務化されることを恐れて精神のバランスを崩す人が増えているけれど、そんなの当然じゃないか。実際に戦地で戦うかどうかに関わらず、これまで描いてきた夢や人生を一時的にでも諦めなければならないし、兵役が終わっても戦争に関わった事実は一生続くんだよ。冷戦時代の兵役と違って、今の兵役は世界各地でフランスが絡む紛争が既に起きているから、実際に派兵されるリスクは高いし、国内の警備にあたる中で、テロリストの攻撃を受けるリスクもある。それが怖いと言ったら弱虫だって言われるの?
戦争に行った兵士たちの心理状態は「ノーマンズ・ランド」という映画が一番現実に近いのではないかと思っている。
2001年のカンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞した作品で、1993年、ボスニアとセルビアの中間地帯<ノー・マンズ・ランド>に取り残された、ボスニア軍兵士チキとセルビア軍兵士ニノ、そして死体と間違われ体の下に地雷を仕掛けられてしまったボスニア軍兵士のツェラが、敵同士なのに極限状態の中で協力せざるを得なくなる話で、当時はこの映画がコメディだという意味が理解できなかった。たとえブラックコメディだとしても。
極限状態に陥った人間たちの愚かさと滑稽さを描いた作品だけど、たとえ今自分がこの状況に置かれても、同じようなことをしてしまう気がする。取り残された3人は滑稽なほど無力で、国連防護軍は驚くほど役立たずで、マスコミの上層部は悲惨な状況を撮影することにしか興味がなく、動いたら地雷が爆発してしまうために地面に横たわったままのツェラにインタビューしてこいなどと命令する。見ているだけでイライラしてくるし滑稽を超えて絶望的な気持ちになってくる。製作したボスニア・ヘルツェゴヴィナ生まれのダニス・タノヴィッチ監督は、1992年に勃発したボスニア紛争の最前線に、自らカメラを持って立ち、300時間以上に渡る戦地の映像を撮影し、多くのドキュメンタリー映画を撮ってきた人で、あまりにも多くの不条理の前では、残酷さと愚かさと滑稽さは紙一重なのかもしれない。
ニノは敵であるチキに撃たれて怪我をしているけど、2人で助けを呼ぶために協力したりタバコを分け合ったりしているうちに距離が縮まり「君の名前を聞いていないけど、僕の名前はニノだ」と握手を求めてしまう。すると、チキがものすごく怒るんだ。「自己紹介なんか必要ないんだよ!電話番号や名刺でも交換したいってのか?次に会うときは照準越しに銃で撃ち合うんだぜ」。また別の時には、お互いの国を責めて喧嘩になる。「お前たちが戦争なんか始めたせいで、こんなことになっちまったじゃないか」、「何言ってんだ、始めたのはお前たちじゃないか」2人ともそれ以上の理由なんて聞かされていないから、同じような悪口を繰り返すことしかできない。恨みもなく素性も知らず、殺す理由も意味もない相手を、敵国の人間だというだけで撃たなければならないのが戦争だ。
今もよく思い出す作品だけど、感動する作品とかそういうんじゃない。この映画に出てくる人たちは、今この瞬間にも実際に戦場にいる人たちなんだよ。名作と呼ばれる昔の戦争映画のように、名誉とか勇気とか愛国心とか兵士同士の友情とか尊敬とか、そんなのは戦争を美化する言い訳で、少なくても前線では、敵が誰なのか、戦争をする意味もよくわからないまま逃げることもできずに死んでいく若い兵士たちが殆どなのではないかと思うんだ。
滑稽で愚かなのは無力な人間たちじゃなくて戦争そのものだ。どうせ滑稽ならば、いくら現実的じゃないと笑われても、戦争をせずに解決する方法を根気よく探し続けることを選びたいと思う。