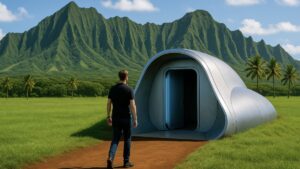CNRS
CNRSとCEAが牽引する「研究立国フランス」の底力
フランスは、ヨーロッパの中でも「公的研究機関による特許出願数」で20年以上にわたりトップの座を守っています。
最新の欧州特許庁(OEB)の報告によると、2001年から2020年の間にフランスの公的研究機関が出願した特許は2万5,000件を超え、ヨーロッパ全体の約4割を占めています。
これは、フランスの研究力が今もなお世界の最前線にあることを示すものです。
トップを走るのはCNRSとCEA
特許の出願数で特に目立つのは、国立科学研究センター(CNRS)と原子力・代替エネルギー庁(CEA)の2機関です。
どちらもフランスの科学技術を支える中核的な存在で、研究分野も広く、基礎科学からエネルギー、情報技術まで多岐にわたります。
欧州特許庁の統計によると、
- CNRSは2000年代初めの特許出願が約1,600件でしたが、直近5年間では3,100件以上と倍増しました。
- CEAも同じく1,100件から2,800件超に増加。
- 医学・生命科学系の国立衛生医学研究所(Inserm)も、500件台から1,400件以上へと大幅に伸びています。
この3機関が、フランスの特許出願の中心的役割を果たしているのです。
医療・半導体・AIなど、戦略分野で強みを発揮
フランスの研究者たちが力を入れているのは、世界的にも注目されている以下のような分野です。
- バイオテクノロジー
- 医薬品開発
- 医療機器や診断技術
- 半導体や計測技術
- デジタル・AI関連技術
病院も研究の最前線に
意外かもしれませんが、フランスでは病院も多くの特許を出願しているのです。
大学附属病院(CHU)は、単に治療を行うだけでなく、医療技術の開発にも積極的に取り組んでいます。
なかでもパリ公立病院連合(AP-HP)は特許出願数が1,968件で、ヨーロッパ全体の約11%を占めており、これはデンマークのコペンハーゲン大学病院やスウェーデンのカロリンスカ研究所を上回る数字です。
このほかにも、
- ガン治療のギュスターヴ・ルッシー研究所(12位)
- グルノーブル大学病院(15位)
- ナント大学病院(18位)
- マルセイユ大学病院(24位)
- リール大学病院(25位)
など、フランス各地の病院が上位にランクインしています。
医療研究の中心分野
大学病院が特許を出している分野は、次の4つが中心です。
| 分野 | 全体に占める割合 |
|---|---|
| 医薬品関連 | 31.3% |
| バイオテクノロジー | 25.4% |
| 医療技術 | 24.0% |
| 生体材料分析 | 8.4% |
これらの分野では、病院と大学、研究機関がチームを組んで研究を進めています。
OEBは、「フランスの大学病院群は、ヨーロッパで最も活発な医療イノベーションのエコシステムの一つです」と評価しています。
研究とスタートアップの連携がカギ
フランスの特徴のひとつは、研究機関とスタートアップの連携が非常に活発なことです。
大学や病院が単独で特許を出すのではなく、ベンチャー企業と共同出願するケースが多く見られます。
フランス国内では、公的研究機関や大学、病院とつながりを持つスタートアップが約550社あり、そのうち525社がフランスの研究機関から生まれた企業です。
これらの多くが、ヘルスケアテクノロジー(医療分野)や情報技術に関わっています。
欧州特許庁からの評価と今後の課題
欧州特許庁のアントニオ・カンピノス総裁は次のように述べています。
「公的研究は、ヨーロッパ最大の強みのひとつです。この調査は、研究機関や大学病院の重要な役割を示しています。彼らの発明はヨーロッパの競争力を高めています。」
そして、こう付け加えています。
「研究の成果を社会や産業にもっと早く届けるためには、機関同士の連携をさらに強化し、研究成果の実用化を加速させる必要があります。」
研究と社会をつなぐ仕組み
フランスは、国立研究機関や大学病院が連携し、医療や科学技術の発展を支えています。
CNRSやCEA、Insermなどの研究所が出す特許は、国の知的財産そのもの。
そこから生まれる技術やスタートアップが、未来のイノベーションを生み出しているのです。
「研究と社会をつなぐ仕組み」を持ち続けること
それこそが、フランスが長年ヨーロッパのリーダーであり続ける理由なのかもしれません。