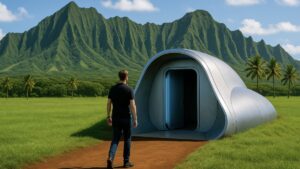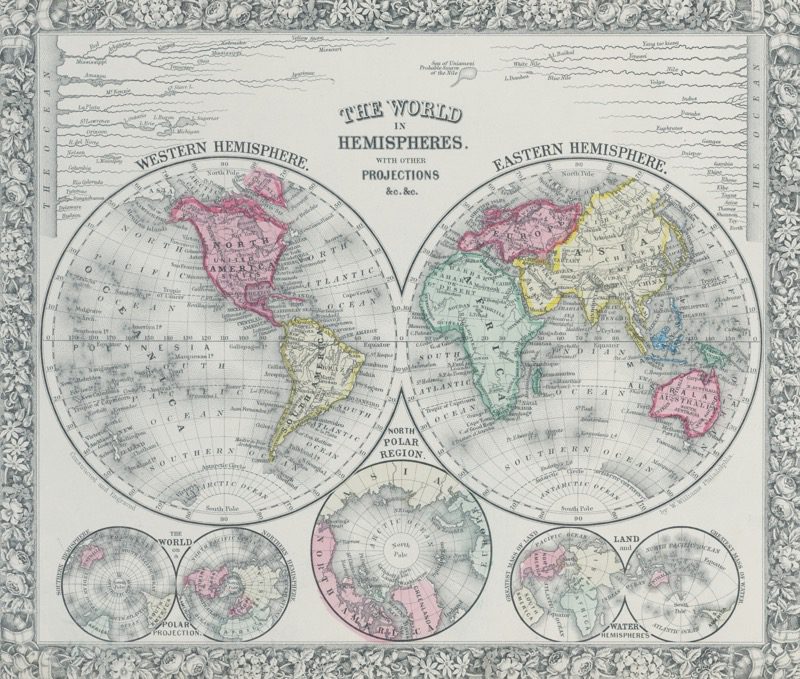
執筆者「ドミニク・モイジ」氏の略歴
ドミニク・モイジ氏は1946 年生まれのフランスの地政学者兼作家で、フランス国際関係研究所(IFRI)共同創設者・上席顧問。現在ハーヴァード大学政治学部客員教授。他に欧州大学院大学教授、およびパリ政治学院教授も務めています。
国際関係と中東の専門家で、Les Échos、Le Monde、Financial Times、New York Times、Die Weltおよびその他の日刊紙に記事を掲載しており、下の文章は、Les Échos紙の2024年10月28日号の記事をまとめたものです。
2009年に出版された著書『The Geopolitics of Emotion / 感情の地政学―恐怖・屈辱・希望はいかにして世界を創り変えるか』はベストセラーとなり、日本語版はAmazonからも購入することができます。

最近は世界中で起こる戦争や紛争などの影響もあって、地政学に興味を持つ人が若い人にも増えているらしいね。地政学では、その土地の宗教や民族、文化に注目することが多いけど「感情の地政学」は人々の感情から地政学を考える、面白い視点の本だと思う。
地政学って何?というかたには、まずは田素弘氏の『紛争でしたら八田まで』を読んでみることをオススメします。麻生元総理の愛読書なんだそうです。
日本の視点から見た世界と、ヨーロッパの視点から見た世界の違い
ますます野蛮化への道を辿る不安な世界の中では、日本は一見すると安らぎのオアシスのように見えたが、それは表面的な印象に過ぎない。
「菊と刀」。第二次世界大戦直後にアメリカの人類学者ルース・ベネディクトによって出版された日本に関する本は、今でも色あせていない。ただし、時とともに、激しさよりも穏やかさが決定的に優勢となった。
先週、東京で講演を行うよう招かれた私は、中東とウクライナでの戦争、アメリカ選挙の不確実性、そしてフランスの国内政治の変動から、物理的にも感情的にも遠く離れたこの国に滞在できることを喜んでいた。
しかし、グローバル化された世界において、東京から見た世界はヨーロッパから見た世界とそれほど異なるのだろうか?
いくつかの重要な違いはあるものの、答えは「否」である。ヨーロッパ人と同様に、日本人(もちろん、エリート層のレベルで)は、アメリカの選挙結果を焦りと不安を持って待っている。悲劇的な最期を迎えた安倍晋三元首相は、ドナルド・トランプを懐柔しようと努めたが、(特にゴルフ場でと言われている)アメリカ大統領は聞く耳を持たず、パートナーであるはずの日本の首相に高慢な態度で接していた。
過去の亡霊と未来への義務の狭間で
2025年1月にドナルド・トランプがホワイトハウスに戻ってくる可能性は、日本人とヨーロッパ人に、ポストアメリカの世界における自らの運命、特に安全保障をより責任を持って担うことを促すはずだ。
しかし、日出ずる国でも欧州連合の大多数の国々と同じような障害、同じような行き詰まり-こちらの表現の方が的確ではあるが-が見られる。
日本は中国に対し責任ある毅然とした政策を定義することに苦心しており、それはヨーロッパのロシアに対する態度と同様であると言えよう。
第二次世界大戦後の憲法的制限の囚人となっている日本は、自衛隊しか持つことができない。韓国(或いは台湾)との「複雑な」関係を完全に克服できない日本は、ソウルとの無条件の関係改善が重要課題であることをよく理解している。
中国の存在感が増し、アメリカの存在感が低下する世界では、西洋諸国間にはアジアのより強い一体性と連帯が必要であり、過去の亡霊は、現在と未来の要望の妨げとなってはならない。
2024年のノーベル平和賞が広島・長崎の被爆者団体に授与された後、日本政府は単に満足の意を表明するだけでなく、世界的な核軍縮運動の先頭に立つこともできたはずだ。しかし、受賞した団体の「左翼的な」性質に対して、ある種の戸惑いを見せることになった。
ますます攻撃的なナショナリズムを示す中国の台頭-最近の台湾包囲演習にも表れている-に直面して、日本はアメリカの保護に代わる選択肢は存在しないと言う意見で一致しているようだが、実際は、アメリカはもはや昔と同じではないと、ある種の諦めを持って認識している。更にドナルド・トランプがホワイトハウスに戻った場合、まったく予測不可能なパートナーになるかもしれない。
アジア人の大多数が自分たちをアジア人として認識していない
日本のジレンマをより複雑にしているのは、ポピュリズムの台頭にもかかわらず、共通のアイデンティティの感覚を持つヨーロッパ人とは異なり、アジア人の大多数が自分たちをアジア人として認識していないことだ。「アジア」とは西洋が発明した概念であり、それは極めて多様な地理的、文化的、政治的現実を表現するためのものだ。
概念の中心が、中国の文明的役割の重要性を表現する「中華」であったとしても、そしていまだにそうであるとしても、文化と政治文化は異なるのである。
日本から見たヨーロッパは、遠い存在であり、かつてないほど不確実に見えている。
しかし太平洋におけるフランスの存在は大きく、ニューカレドニアでの暴動を注意深く見守る日本の友人たちは、それがあとどのくらい続くのだろうかと問いかける。
インドはまだ、アジアにおける中国とアメリカの間の均衡勢力になりたいという願望を実現できていない。現時点では、まだ中国と同じカテゴリーには遠く及ばない。
日本が直面している主要なジレンマは、ヨーロッパのそれとよく似ている。今日の世界では、アメリカに代わる選択肢はない。しかし、来る11月5日以降も、アメリカは選択肢であり続けるのだろうか?
いっぽう中国は、ますます集中化する権力の方向性によって国が強化されるというよりも、むしろハンディキャップを負っている。この変化は、私の日本滞在中に出会った中国の経済エリートたちを困惑させており、彼らはほぼ公然と懸念を表明している。彼らを悩ませているのは表現の自由の欠如ではなく、「国家資本主義」という長年成功してきた方式が変化して以来、習近平が作り出した新しい状況が創造性と成長に与える悪影響こそが問題なのだ。国家の要素がますます強まり、資本主義の要素がますます弱まっているのである。
中東に対する距離を置いた視線
地理的、歴史的、文化的な明白な理由により、日本の視線がより距離を置いている地域があるとすれば、それは中東である。
多神教が一神教よりも優勢である日本のような国では、ユダヤ教、イスラム教の存在は少数派であり、立場的に影響を受けることは少ない。
今日の中東問題においては、日本のエリートたちは西洋の懸念を共有しているようだ。イスラエルは短期的な安全保障を強化する一方で、長期的な正当性を損なったのではないか?
おそらく将来、拡大された安全保障理事会の常任理事国になることを目指しているため、日本は特にイスラエルのUNIFIL(国連レバノン暫定軍)への攻撃に困惑している。しかし、それ以上に、アントニオ・グテーレス国連事務総長がカザンでのBRICS首脳会議に出席したことに困惑している。プーチン大統領を批判しながらも正当化することは、国連の非正統性を意味するのではないだろうか?
国連の忠実な支持者である日本は、西洋諸国の大多数と同様に、国連事務総長の行動に困惑している。国連にはまだ普遍的な使命があるのか、それとも「グローバル・サウス」の不満の相談窓口に過ぎないのだろうか?
最後に、「残虐な世界の中のほんの少しの優しさ」。有名な広告のパロディを使えば、これが私に映った日本の姿である。

内からと外からでは見えるものが違うことが往々にしてあるけど、国際政治や外交については特に外から見たほうが、はっきり見える部分が多いと思うし、正しくても間違った見方であっても、意見に耳を傾けることって大切だと思うんだ。
フランス人には漫画や食文化などの日本文化が好きな人が多くて、文化的に好意的に受け取られることが多いけど、政治・外交的には日本に対する辛辣な意見も多いんだよね。ネガティブな意見の多くは、日本はアメリカの意見に常に無条件賛成で、国際政治や外交の場では消極的な発言しかしていない印象で(中国などの周辺国に強く出られても、遺憾に思うという公式な回答が多いけど、それって残念に思うくらいのニュアンスだよね。)、日本人の大人しくて我慢強いイメージと戦争でのイメージが結びつかず、理解しにくいという人は今だに多い気がする。
まあフランスはアメリカと意見がぶつかることが多くてライバル心も強いし、外交の場で顰蹙を浴びるようなことでもはっきりと意思表示してきた国だから、顰蹙を買う意見よりも意見がないということに対してのほうが全般的に手厳しい傾向がある。(日本と逆じゃない?)
ただ、2024年のノーベル平和賞を受賞したのに、核軍縮のアピールを殆どしなかったことが残念だというのは本当にそうだと思う。日本は右翼、左翼に対して敏感になりすぎるところがあるんじゃないかな。たしかに歴史的に過激な事件も多かったけど、世界的には右翼の意見も左翼の意見も両方あって当然という国は多いし、日本には言論統制はないということを示すためにも、右翼寄り、左翼寄りに関わらず、国民の声をちゃんと外に伝えるべきだと思うんだ。ドイツと同様に、今も戦争に関して発言することに後ろめたい気持ちがあるのかもしれないけど、全ての国に気を使いすぎて結局どこからもマイナスの評価になってしまうというのは日本特有の問題なんじゃないかと思うんだ。
このタイミングでの受賞は、唯一の被爆国としてはっきりと意見することを、受賞を決めた側も他の国も望んでいたと思うんだよ。たとえ今からでも、どんな理由があっても核戦争は駄目なんだ、と世界に向けてはっきりとアピールすれば、日本がちゃんと意思表示をしたという記憶となって残ると思うしね。
彼の著書の中にはちょっとステレオタイプ的な見方もあるけど、この記事の内容は比較的に好意的に、でも的確に日本を観察していると思う。特に最初と最後の一文、安らぎのオアシスとまではいかない「残虐な世界の中のほんの少しの優しさ」って褒め言葉にちょっとした皮肉も添えて(これがなきゃフランス人じゃない)、日本を上手く言い表している気がする。