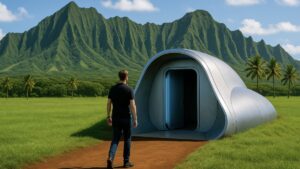欧州における水素列車の状況
水素列車とは?
水素列車は、車上で水素と酸素を反応させて電気を取り出し、その電力でモーターを回して走る非電化区間向けの電車です。屋根の上の高圧タンクに水素を貯蔵し、車内の燃料電池で発電し、加減速のピークは補助電池が受け持ちます。
走行時に排出するのは水で、ディーゼル気動車の代替となるゼロエミッション車両として各国が導入を進めています。電化工事が難しい地方線でも既存の線路と駅設備を活用でき、運行側はダイヤや保守の運用を大きく変えずに導入しやすいのが特徴です。
一方で、水素の製造や輸送、圧縮や貯蔵の安全設計、補給設備の整備など、エネルギー側の体制が不可欠です。鉄道事業者、エネルギー企業、自治体の三者が計画段階から連携し、車両と補給を同時に設計することが、導入の成否を左右します。
車両の性能指標は最高速度、加速度、航続距離、補給時間、稼働率などで評価され、既存の電車運用に近い応答と終日運用を両立できるかが実務の焦点です。水素列車とは、水素燃料電池を搭載し、水素と酸素の化学反応によって電力を発生させて走行する列車です。走行時に排出されるのは水蒸気のみであり、二酸化炭素を排出しないため、環境に優しい次世代の鉄道車両として注目されています。
水素列車はディーゼル列車と比べて、二酸化炭素を排出しないため環境負荷が低く、騒音も少ないという利点があります。非電化路線において、ディーゼル列車を置き換える有効な手段として期待されています。
メリットとデメリット | 排出削減と初期投資のバランス
水素列車は、車上で水素と酸素を反応させて電気を取り出し、その電力でモーターを回して走る非電化区間向けの電車です。屋根の上の高圧タンクに水素を貯蔵し、車内の燃料電池で発電し、加減速のピークは補助電池が受け持ちます。
走行時に排出するのは水で、ディーゼル気動車の代替となるゼロエミッション車両として各国が導入を進めています。電化工事が難しい地方線でも既存の線路と駅設備を活用でき、運行側はダイヤや保守の運用を大きく変えずに導入しやすいのが特徴です。
一方で、水素の製造や輸送、圧縮や貯蔵の安全設計、補給設備の整備など、エネルギー側の体制が不可欠です。鉄道事業者、エネルギー企業、自治体の三者が計画段階から連携し、車両と補給を同時に設計することが、導入の成否を左右します。
車両の性能指標は最高速度、加速度、航続距離、補給時間、稼働率などで評価され、既存の電車運用に近い応答と終日運用を両立できるかが実務の焦点です。水素列車とは、水素燃料電池を搭載し、水素と酸素の化学反応によって電力を発生させて走行する列車です。走行時に排出されるのは水蒸気のみであり、二酸化炭素を排出しないため、環境に優しい次世代の鉄道車両として注目されています。
水素列車はディーゼル列車と比べて、二酸化炭素を排出しないため環境負荷が低く、騒音も少ないという利点があります。非電化路線において、ディーゼル列車を置き換える有効な手段として期待されています。
従来のディーゼル列車と比較した場合の水素列車は、大きく以下の4点となります。
- CO2排出量の削減:
水素燃料電池は、水素と酸素の化学反応によって電気を発生させ、その際に排出されるのは水のみです。このため、走行中のCO2排出量がゼロとなり、地球温暖化対策に大きく貢献します。 - 大気汚染の改善:
ディーゼル列車は、走行中に窒素酸化物や粒子状物質などの大気汚染物質を排出します。一方、水素燃料電池列車はこれらの有害物質を排出しないため、大気質の改善に役立ちます。 - エネルギー効率:
燃料電池は高いエネルギー効率を持ち、従来のディーゼル列車に比べて運行コストを削減できます。 - 静音性:
水素列車は電動であるため、運行時の騒音が少なく、周囲の環境に配慮した運行が可能です。
ベルリン北部の運用 | 折返し15分補給と本数維持
ベルリン北部のハイデクラウトバーンでは、地域事業者が7編成の水素列車を導入し、2024年末のダイヤ改正に合わせて定期運行を開始しました。導入の狙いは、非電化区間のゼロエミッション化と運行コストの安定化です。効果として、年間のディーゼル消費を大幅に削減し、CO2も数千トン規模で抑制できる見込みが示されています。
ニーダーバルニマー鉄道は、ハイデクラウトバーン線でMireo Plus Hを定期運用しています。折返し駅と基地でのまとめ補給を前提に、充填時間は約15分を目安とし、運転士交代と日常点検と並行できる手順に整えました。
ダイヤ乱れ時の安全弁として移動式補給設備を用意し、設備点検や道路事情による遅延をダイヤに反映できるよう余裕を確保しています。エネルギー側では、再生可能エネルギー由来の水素供給を基本方針とし、沿線近傍で製造・供給拠点を整備中です。
2025/09/12にヴェンジッケンドルフの新プラント起工式が行われ、2026年からの独占供給開始を計画しています。運用管理は、運行本数、所要時間、折返し時分の三要素を固定し、季節条件や乗車率に応じて予防保全の頻度を調整する方式です。設備停止時に備えた代替輸送計画も作成済みで、情報提供手順と連絡先を統一しました。ゼロエミッション化の年度目標を掲げ、電池電車との使い分けを路線単位で決めています。
バイエルンの段階導入 | 小規模開始から2年半で拡大
バイエルン地方鉄道(Bayerische Regiobahn)は2024/12/16から東アルゴイ〜レヒフェルトで一部列車を水素車両に置き換え、のちにアマーゼーやアルトミュールタールへ拡大する計画です。約2年半のパイロット期間で、勾配、停車密度、気温、乗車率が航続や補給に与える影響を比較検証します。走行ログは燃料電池出力、電池のSOC・温度、回生量、消費率、充填時間を中心に収集し、季節ごとのパラメータマップを作成します。
保守では、燃料電池と圧縮機のユニット交換時間を測定して標準工数化し、予備ユニットの配置数を見直します。2025/04にはミュールドルフ拠点の非電化幹線向けに3本を追加発注し、Südostbayernbahnでの営業入りを2026年末に設定しました。乗務員教育は電車運転手順に近い形で統一し、非常時の隔離手順、通報経路、避難誘導の訓練を定期化しています。導入規模を急拡大せず、線区ごとの実データに基づいて置き換えを進めるのが前提です。
いずれの地域も、実証ではなく定期ダイヤの中で運行しており、利用者は通常の列車として乗車できます。車両調達、補給設備、運行計画は当初から一体で設計され、担当主体(鉄道事業者、エネルギー会社、自治体)が役割分担を明確化しています。
今後は運行データの蓄積に合わせ、補給能力の調整、保守周期の最適化、編成数の微調整を行い、稼働率の安定を優先します。数字と手順を固定し、段階的に広げる進め方が基本です。
Mireo Plus Hの仕様 | 燃料電池+電池のハイブリッド設計
Mireo Plus Hは、屋根上の高圧水素タンク、車内のPEM燃料電池、車上のトラクション電池で構成されます。加速時は電池がピーク電力を受け持ち、巡航は燃料電池が担当し、減速時の回生電力は電池へ戻します。
最高速度は160km/h、二両編成で駆動出力は約1.7MW、最大加速度は1.1m/s²を想定します。航続距離は運用条件で変動しますが最大1200km、補給時間は約15分です。
プラットフォームは電池電車Mireo Plus Bと共通化を進め、車体、運転台、保守手順の共通部品化で教育・在庫コストを削減します。燃料電池はモジュール単位の交換を前提とし、劣化監視は出力、温度、振動の組み合わせで行います。
安全設計はタンク遮蔽、圧力監視、漏えい検知、強制換気の多重化が基本です。台車・ブレーキの整備周期は従来電車と同等を目標とし、夜間にまとめて点検できる工数配分に合わせて設計しています。
補給と体制|インフラ・資金・ガバナンス
補給インフラは常設ステーションと移動式設備を併用します。常設は基地・終端駅に配置し、移動式は設備停止時や工事中のバックアップに使用します。鉄道事業者、エネルギー会社、車両メーカー、自治体が費用と役割を分担し、資金は公的補助と低利融資を組み合わせます。
保安規程は消防・警察との連絡体制を含めて定め、周辺住民への説明手順も初期から計画に入れます。稼働率を上げるうえでは、燃料電池や圧縮機の予備機を適正に持ち、部品リードタイムに合わせた発注点を設定します。運行管理は、折返し時分、留置位置、回送列車の設定に補給フローを組み込み、ダイヤ乱れ時の影響を局所化します。
ベルリン・ブランデンブルク運輸連合は、地域鉄道のゼロエミッション化を2037年に設定し、線区条件に応じて水素と電池の使い分けを採用しています。運賃水準への影響を最小化するため、長期契約と保守包括契約の組み合わせが基本です。
iLintの教訓 | 稼働率を左右する供給網と信頼性
ヘッセン州タウヌス線では、アルストムのCoradia iLintで不具合や部品供給遅延が重なり、2025年末までディーゼル代走の判断が出ました。エルベ=ヴェーザーでも一時的に燃料電池の確保が難しく、運用制約が発生しました。
ここから得た教訓は、稼働率を支えるのは車両単体の信頼性だけではなく、補給設備の稼働、予備ユニットの配置、サプライチェーンの冗長化という複合要素だという点です。シーメンスはモジュール交換前提の設計と共通プラットフォームで保守負担を平準化し、事業者側は夜間点検の標準工数化、診断ソフトの更新、突発停止の削減に取り組んでいます。
運転士教育は通常運転・非常時対応・通報経路を明文化し、訓練を定期化しました。こうした積み上げにより、運行再開や増備判断の材料が揃いつつあります。課題は事実として共有し、手当を同時に進めるのが実務的です。
各国の現在地 | 欧州・北米・アジアの導入比較地
カリフォルニア州サンバナディーノ郡では、スタッドラーのFLIRT H2が2025/09/13に旅客営業を開始しました。北米規格での運用実績が蓄積され、短区間・高頻度のデータが今後の導入判断に活用されます。
フランスではアルストムが近代化プログラムを進め、線区ごとに次期構成を検討しています。スイスはスタッドラーが燃料電池とバッテリーの統合プラットフォームを磨き、欧米案件に展開しています。
日本は水素ハイブリッドの試験走行を継続し、山間の非電化区間を念頭に評価中です。中国は都市間向けの水素高速試作を発表し、供給網と安全規格の整備を進めています。
各国共通の論点は、グリーン水素の供給量とコスト、補給網の標準化、車両と設備の保守体制です。結論は単純で、電池電車と水素列車の使い分けを地域条件に合わせて行い、運行と補給の両面で無理のない設計を選ぶこと。ドイツの現在地は、そのための実務データを着実に積み上げる段階にあります。