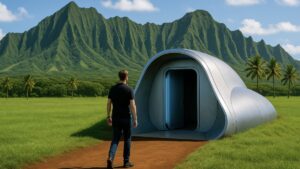食の大国フランスが抱える苦悩
2025年2月22日(土)から3月2日(日)まで、パリ万博公園(ポルト・ド・ヴェルサイユ)で第61回「Salon International de l’Agriculture(SIA/国際農業見本市)」が開催されました。
この見本市は、毎年2月に開かれるフランス農業最大の祭典で、国内外に向けて「食と農業の国・フランス」の魅力をアピールする舞台です。普段は家族連れや観光客でにぎわい、各地の特産品や家畜の展示、最新の農業技術の紹介などが行われます。
しかし、昨年2024年の開催では、この華やかなイベントがかつてない緊迫した空気に包まれました。
2024年、見本市が迎えた歴史的転換点
2024年2月24日、エマニュエル・マクロン大統領が会場入りした瞬間、外では農業者たちがトラクターのクラクションを鳴らし、「政府は裏切り者だ!」という怒号が響き渡りました。さらに、警備隊の催涙ガスが白煙となって会場周辺を覆い、来場者やメディアを驚かせました。
この騒動は、EU最大の農業国フランスが直面している深刻な現実「農業の構造的な危機と政府への不信感」を象徴する出来事でした。
崩れゆく農業大国の現実
数字が語る危機の深層
- 後継者不足
農業人口の高齢化が進み、3人の農家が引退しても、新たに就農する若者はわずか1人。多くの農地が耕作放棄や企業による買収の危機にさらされています。 - 輸入依存の加速
フランスは「食の自給率が高い国」と思われがちですが、実際には果物の約70%、鶏肉の約50%を輸入に頼っています。スーパーの棚に並ぶ食材の多くが、すでに海外産なのです。 - 農業貿易黒字の急減
2000年代初頭には約140億ユーロあった農産物の貿易黒字は、2024年には49億ユーロにまで減少。過去10年間で、フランスは世界市場で70〜80億ユーロ相当のシェアを失いました。これは単なる数字の減少ではなく、輸出競争力や農業の国際的地位の低下を意味します。
農家の収入が直面する厳しい現実
フランス国立統計経済研究所(INSEE)の調べによると、2021年時点でフランス国内には林業を除き約39万戸の農家があり、その平均月収は1,860ユーロ(約29万5,000円)でした。
しかし、この数字はあくまで全体の平均であり、農業の種類や規模、地域によって収入には大きな差があります。
例えば、
- 牛の飼育農家 … 平均1,480ユーロ(約23万5,000円)
- ワイン生産者 … 平均2,760ユーロ(約43万7,000円)
- 大規模穀物農家 … 平均2,150ユーロ(約34万円)
これらの金額を、2021年当時のフランス新卒平均初任給2,250〜2,670ユーロ(約387,000円〜約459,000円)と比べると、ワイン生産者でも新卒の初任給と同程度、その他の農家の収入は、新卒の初任給を大きく下回っていることがわかります。経験を積んだ大規模農家でさえ、新卒の給与に届かないケースのほうが多いのです。
特に深刻なのが、ヤギ・羊・馬の飼育農家です。彼らの平均月収はわずか680ユーロ(約10万8,000円)。しかも家畜の世話は農閑期がなく、年間を通して手間がかかる仕事です。それでも農業収入だけでは生活できず、副業や別収入に頼らざるを得ないのが現状です。
貧困率と農家数の減少
フランス全土の18%の農家が貧困ラインを下回る生活を送っています。農家戸数も、2001年の97万戸から2021年には39万戸まで激減。これは単なる数字の変化ではなく、後継者不足や採算悪化による廃業が急速に進んでいることを示しています。
さらに2021年以降、燃料費や飼料費、肥料などの経費がわずか2年で25%も上昇。一方で販売価格や収入は伸び悩み、特に経費負担が大きい酪農・畜産農家の廃業が急増しています。こうした状況から、「子どもには農家を継がず、普通の職業に就いてほしい」と願う親が大半です。
EU規制に対する農家の不満
フランス農家の間には、EU(欧州連合)が定める規制や政策に対する不満が根強くあります。主なポイントは次の通りです。
- 環境規制の厳格化
- ネオニコチノイド系殺虫剤の全面禁止
- 動物福祉基準の強化(飼育環境の改善や密飼い規制)
- 生物多様性保護のための農地管理義務
これらは環境保護の観点から重要ですが、設備投資や管理コストの増大を招き、小規模農家には重い負担となっています。
- 農産物価格の低迷
- EU共通農業政策(CAP)による補助金はあるものの、金額が不十分と感じる農家が多くなっています。
- EU内での競争激化や、低価格の輸入農産物(特に南米や東欧産)の流入により、国内農産物の販売価格が押し下げられている状況です。
- 規制の複雑さ
- EUの農業関連規則は申請や報告が多く、遵守のために時間とコストがかかります。
- 特に人員や事務能力に限界がある小規模農家では、制度対応が経営負担になっています。
- 食品安全基準の影響
- 農薬使用の制限や、輸送・保管方法の厳格化などにより、設備更新や管理体制の改善が必要となりコストが増加しています。
- 気候変動対策への対応
- 温室効果ガス排出削減の義務化や、持続可能な農法への転換が求められています。
- 新技術導入や設備改修が必要となり、これが追加負担となっています。
このように、フランス農家は低収入・高コスト構造の中で、EU規制や国際競争、気候変動対策といった複合的な課題に直面しています。特に若手や小規模農家ほど影響が大きく、将来の担い手不足が深刻化しているのが現状です。
政策の光と影
フランスの農家は、EUが定める厳しい農業規制について、「経営への負担を軽減し、より現実的で持続可能な形で導入してほしい」と改善を求め続けています。規制の目的は環境保護や食品安全の向上ですが、現場の農家にとってはコスト増や作業負担の増加となり、特に小規模農家では経営を圧迫する要因になっています。
こうした状況の中、農業者の経済的安定を図るために導入されたのが EGalim法 です。
EGalim法とは?
正式名称は、「農業および食料分野における商業関係の均衡並びに、健康で持続可能かつ誰もがアクセスできる食料のための法律」。2018年にフランスで制定され、農業者と食品産業の取引関係を改善し、農業者の所得向上と食品の質の確保を目指しています。
背景には、農産物の価格が過度に低く抑えられ、農家の経営を圧迫していた現実があります。マクロン大統領が主導した「食料全体会議(États généraux de l’alimentation)」 の議論を受け、農家が生産した作物や畜産物を正当に評価し、適正価格で取引できる仕組みを整えるために導入されました。
主な規定と内容
フランス国立統計経済研究所(INSEE)の調べによると、2021年時点でフランス国内には林業を除き約39万戸の農家があり、その平均月収は1,860ユーロ(約29万5,000円)でした。
しかし、この数字はあくまで全体の平均であり、農業の種類や規模、地域によって収入には大きな差があります。
例えば、
- 契約条件の優先
農産物の取引契約では、生産者(農業者)からの提案を基に条件を決めることが義務化されました。これにより、価格交渉で農家の立場が強化されます。 - オーガニック・持続可能な食材の割合
学校給食や公共食堂の食材について、20%をオーガニック、50%を高品質で持続可能な食材 にすることが目標として定められています。これは、2017年の規定を引き継ぎ強化したもので、子どもの健康と環境保護の両面を意識した施策です。 - 生産コストの考慮
価格決定においては、生産コストを反映することが義務付けられ、契約も必ず書面で交わすよう規定されています。これにより、原価割れでの販売を防ぎ、農家の収入安定を図ります。 - 食品トレーサビリティの強化
食品がどこで、どのように生産されたかを追跡できる体制を整え、消費者が安全で持続可能な商品を選びやすくします。
法律がもたらした影響
EGalim法は、農業者の収入安定と食品の品質向上を両立させることを目的としており、取引の透明性や公正性を高める効果が期待されています。一方で、オーガニックや持続可能な食材の割合を増やすためには、生産者・加工業者・流通業者すべてに対応コストが発生し、小規模農家や予算の限られた自治体では負担が大きいという課題も残っています。
つまり、EGalim法は「農業者を守る盾」であると同時に、「新たな負担を生む規制」でもあり、その光と影が今も議論され続けているのです。
EGalim法の功罪
農家の交渉力を高め、公正な取引を促すことを目的に導入されたEGalim法。しかし、その理想とは裏腹に、思わぬ逆効果を生んでしまいました。
本来は農家が価格交渉で優位に立ち、持続可能な農業を守るはずのこの法律ですが、実際には大規模流通業者が海外からの調達を拡大する結果となりました。背景には、この法律が細かく目標や条件を設定したことによる事務負担の増加があります。
農家は本業である農作業に加えて、契約書の締結やオーガニック認証のための証明書作成、品質検査、監査対応など、多くの新しい手続きが必要になりました。給食や公共食堂向けの食材を扱う流通業者も同様で、新たな規定への対応に時間とコストがかかるようになったのです。
結果として、流通業者はコストを抑えるために、より安価な農産物を供給できる生産者 – 多くは海外の業者 – を探すようになりました。フランス国内の農家は価格競争の中で不利な条件で契約を結ばざるを得ず、その負担が農家側に重くのしかかっています。
パリ郊外で野菜を生産するピエール・マルタンさん(49歳)は、苦渋の表情でこう語ります。
「補助金が出るとはいっても、新たに増えたコストをカバーできる額じゃない。規制が厳しくなればなるほど、その抜け穴を突く業者が出てくる。そしてそれが見つかれば、また規制が厳しくなる。まるで、あちこちに仕掛けられた鼠取り器の中を歩いているようなものだ。」
この言葉は、理想を掲げた政策が現場に与える負担の大きさ、そしてその影響の連鎖を端的に表しています。EGalim法は農業の公正さを守る「盾」である一方で、農家を締め付ける「枷」にもなりかねない – そんな現実が、現場から浮かび上がっています。
共通農業政策(CAP)を巡って分断するEU
EUの農業政策は、加盟国全体に共通のルールと補助制度を適用する「共通農業政策(CAP)」によって支えられています。1962年に始まったこの仕組みは、農家の所得を安定させ、食料の安定供給と価格の維持を目指してきました。現在もEU予算の約3割を占める最大規模の政策分野であり、農業に携わる多くの人々にとって欠かせない制度です。
背景には、EUが掲げる「持続可能な農業」への転換があります。農薬や化学肥料の使用を減らし、有機農業を拡大し、家畜に配慮した飼育方法や自然環境の保護を進めるという目標です。こうした環境面での理想は加盟国の多くが共有していますし、気候変動の影響が顕著になった現在、その必要性は否定できません。
しかし、実際に現場で実行しようとすると、地域ごとの事情や経済的負担の違いが表面化し、加盟国の立場が大きく分かれています。
南欧諸国では、近年の干ばつや猛暑が農業に深刻な影響を与えています。スペインやイタリア、ギリシャなどでは、オリーブやブドウ、果樹などの高付加価値作物を守るため、水資源管理や灌漑設備の整備に予算を重点的に配分すべきだという意見が強いです。環境基準を守る重要性は認めながらも、生産量や輸出競争力を損なうような規制強化には慎重な姿勢です。
一方、ドイツやオランダ、デンマークなどの北西ヨーロッパ諸国は、環境保護を最優先にしています。農薬の使用削減や有機農業の拡大、気候変動対策の徹底をCAPの中心に据えるべきだと考えており、農家への補助金も環境条件の達成度に応じて厳格に配分するべきだと主張しています。
さらに、ポーランドやハンガリー、ルーマニアといった中東欧諸国では、小規模農家が多く、CAPの直接支払いが生活基盤の維持そのものに直結しています。環境保護が最優先ではないものの、農業補助金の直接支払いは、環境基準の達成が前提になっているため、基準を守ることが経済的に有利になります。
下の図は、大まかに分けて、規制強化に反対な国(農業の生産性を優先)をオレンジ色で示し、規制強化の推進に賛成な国(環境保護を優先)をブルーで示しています。結局、規制強化に反対する国は、賛成国には数で勝てないのです。

フランス政府はなぜEUに対し、規制の見直しを要求できないのか?
フランスはEU最大の農業国として、環境目標と農業経済の両立を模索しています。国内農業を守りつつ輸出競争力も維持する必要があるため、規制の内容や導入のスピードには慎重で、しばしば他国の主張の間をとる立場をとっています。
このような立場の違いは、CAPの改正や新たな環境基準の導入のたびに鮮明になります。EUの法律は欧州委員会が提案し、欧州議会と加盟国代表で構成されるEU理事会の双方が合意しなければ成立しません。27カ国がそれぞれ異なる農業構造や気候条件を抱えているため、合意形成には時間がかかり、現場の変化に迅速に対応できないという問題もあります。
農業を持続可能な形に変えていくことは、EU全体の共通課題です。しかし、その道筋をめぐっては、気候や経済構造、政策優先順位の違いから加盟国間の溝が深まっています。環境と生産のバランスをいかに取るのかという難題に、EU農業は今まさに直面しているのです。
フランスの農業にとっての国際農業見本市(SIA)の役割
国際農業見本市(SIA)は、フランス農業にとって国内外へ多大な影響を与える重要イベントです。
2025年のテーマは 「フランスの誇り(Fierté française)」。農業を国の団結の象徴として位置づけ、国民にその重要性を再認識してもらうことが狙いです。
2024年のSIAは農民による抗議で混乱しましたが、2025年は雰囲気が一変。より穏やかなムードの中で、フランス農業のポジティブな側面を国内外に発信することに重点が置かれています。
- 国民の農業理解と関心を高める場
SIAは、市民が農業の現状に触れ、農業の重要性や課題を知る貴重な機会です。
テーマに沿った展示やイベントを通じて、食料の価格、品質、安全性など、消費者の関心が高いテーマに関する情報提供や意見交換が行われ、消費者意識の向上にもつながります。 - 経済効果と地域振興
来場者は毎年60万人を超える見込みで、農産物の販売促進やブランド力向上、新たな商談の場としても機能します。
さらに地方の特産品や食文化が紹介され、地域間交流や地方経済の活性化にも寄与します。 - 最新技術とイノベーションの発信
会場では最新の農業技術や生産方法、スマート農業機器、環境保全の取り組みが紹介されます。これにより、生産性の向上や持続可能な農業への移行を後押しします。 - 農業界の意見表明と政府との直接対話
SIAは、FNSEA(フランス農業総連盟)をはじめとする農業団体や生産者が政府関係者と直接話し合える場でもあります。
2024年にはマクロン大統領が農民から激しい抗議を受けたことが象徴的で、ここでの議論が政策に直結することも少なくありません。 - 政策への影響力
SIAの議論や世論の高まりは、政府の農業政策に直接影響します。
2025年の開催直前には、新たな農業方針を示す法律が可決され、今後はEGalim法の見直しや土地利用問題の協議が予定されています。
2025年のSIAで話し合われた主な課題
- 農業政策全般
政府と農業団体が価格・収入・環境規制・土地利用など幅広いテーマで意見交換 - 農産物価格と農家の収入
バイルー首相は「価格と収入こそ最大の課題」と強調。収益改善が急務とされました。 - 水資源の管理
干ばつや気候変動による水不足対策が重要テーマに。効率的な水利用やインフラ整備が議論されました。 - 世代交代と土地問題
後継者不足解消のため、土地の利用や所有権に関する新しい制度設計が検討されています。 - 行政手続きの簡素化
EUの共通農業政策(PAC)申告では、行政が必要情報を保有し、農家は正確性を確認するだけにする案を提示。 - 規制緩和と農家支援
- 環境基準の一部見直し
- 「エコフィト計画」の緩和(農薬使用を半減する計画の柔軟化)
- 農薬販売・使用に関する規制の簡素化
- PAC補助金の支払い規則の緩和
これらは「環境保護より農業の維持を優先する」姿勢の表れです。
- 農業の環境課題への対応
気候変動、生物多様性の喪失、土壌劣化に対する持続可能な農業への移行策が模索されました。 - 輸出促進のための行政簡素化
輸出関連手続きの短縮とコスト削減で、企業の国際競争力を高めることが目的です。
このように、SIAは単なる展示会ではなく、農業の現状を示し、国民と政府、そして国際社会に向けてフランス農業の方向性を示す舞台となっています。
華やかな催しの裏では、価格・収入・環境規制・世代交代といった根本的課題が、現場と政策の両方から同時に議論されているのです。
FNSEA(フランス農業総連盟)の役割と政府との連携
FNSEA(Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles/フランス農業総連盟)は、フランス最大の農業団体で、国内農業者の利益を代表し、政府やEUとの交渉を行う強力なロビー組織です。加盟者は大規模農家から家族経営農家まで幅広く、フランス農業政策の方向性に大きな影響を与えています。
現在、FNSEAは「農業の生産的性質の再確認」を最重要課題のひとつに掲げ、農業を単なる産業としてではなく、国の食料安全保障・地域経済・文化的価値を支える基盤として位置づけることを求めています。
- 「農業の方向性を示す法律」の制定
FNSEAが長年求めてきた「Loi d’orientation agricole(農業の方向性を示す法律)」が、2025年2月20日、国際農業見本市(SIA)開催直前に議会で可決されました。
この法律は、農業と食料の主権を守るための基本方針を明文化したもので、農業を「公益に資する主要な関心事」として農村法に明記する条項が盛り込まれています。FNSEAはこれを、農業の生産的役割を再評価するための「第一歩」と高く評価しました。 - 税制・社会保障負担の軽減
2025年度の財政法案および社会保障財政法案には、FNSEAの要望を受けた農業界向けの負担軽減策が盛り込まれました。政府は、これらの措置により約5億ユーロの国費が投入されると試算しています。主な内容は以下の通りです。- 税制および社会保障負担の軽減:農業経営の収益性向上と新規就農者の参入促進を狙い、社会保険料や税負担を減らす措置を導入。
- 家畜農家への税制優遇:特に牛の飼育農家を対象に、飼育コストを抑えるための税優遇措置を新設。
- 農業退職年金の優遇:退職年金の計算において、過去25年間の最高年収を考慮できるよう改正し、受給額の底上げを実現。
- ディーゼル燃料税の免除
2024年1月、政府が発表した非道路用ディーゼル燃料(GNR)税引き上げ案は、農家の強い反発を招き、南西部を中心に大規模な抗議行動が発生しました。最終的に政府は課税引き上げを撤回し、従来どおりの免除措置を維持することを決定しました。これは農機の運用コスト抑制に直結し、農家からは歓迎されています。 - 政府と農業界の対話姿勢
これらの施策は、政府がFNSEAをはじめとする主要農業団体との対話を重視し、農業界の要求を政策に反映しようとしている姿勢を示しています。フランソワ・バイルー首相も「主要な農業団体が政府の努力を評価している」と強調しました。
ただし、FNSEA内部や一部農業者からは「実際の現場の課題解決には不十分」との声もあり、今後はこれらの政策をどのように実効性ある形で運用していくかが焦点となります。 - 政策への影響力
SIAの議論や世論の高まりは、政府の農業政策に直接影響します。
2025年の開催直前には、新たな農業方針を示す法律が可決され、今後はEGalim法の見直しや土地利用問題の協議が予定されています。
再生への挑戦 – 先進事例に学ぶ
フランスの農業界では、環境負荷を減らしつつ収益性を確保するための新しい取り組みが広がっています。その代表例が、農業協同組合グループ Vivescia が推進する Transitionsプログラム です。
Vivescia Transitionsプログラムとは
この「移行プログラム」の目的は、農業従事者がより持続可能で環境に配慮した農業慣行へ移行するための経済的・技術的な支援を行うことにあります。気候変動や生物多様性の喪失、土壌の劣化といった農業が直面する深刻な課題に対応し、環境と経済の両立を目指します。
具体的な取り組み内容:
- 農業生態学的移行の促進
- 農家が化学肥料や農薬への依存を減らし、土壌や生態系を守る持続可能な農法へ移行できるよう支援します。
- 経済的支援(奨励金制度)
- 環境負荷低減に取り組む農家に対し、努力に応じて1ヘクタール当たり 100〜150ユーロ(約1万6,000〜約2万4,000円) のプレミアムを支給。収入の安定化を後押しします。
- 技術的支援
- 専門家による研修や現地アドバイス、診断サービスを提供。持続可能な農業の実践に必要な知識・技術を習得できるようにします。
- データ収集とモニタリング
- 参加農家から生産や環境指標のデータを収集し、プログラムの効果を検証。結果は改善策の立案にも活用されます。
- ドグマからの脱却(固定観念にとらわれない農業)
- 特定の農法を押し付けるのではなく、各農家の地域条件や経験に合わせた最適解を共に探る姿勢を重視。画一的ではなく柔軟で創造的な農業を奨励します。
成功事例
ノール県の小麦農家 マリー・ルフェーブルさん(42歳) は、精密農業技術を導入し、収量を15%向上させる一方で化学肥料使用量を40%削減しました。
「データを活用すれば、収益性と環境配慮の両立は可能だと実感しました」
デジタル農業の最前線
最新の農業テクノロジーも急速に進化しています。
- AI輪作プランニング:過去50年分の気象データと土壌分析結果を深層学習により解析し、最適な作付け計画を自動提案。
- ドローン監視システム:1ヘクタール単位で病害虫発生を95%の精度で検知、早期対策を可能に。
- ブロックチェーン流通:生産から消費までの流通履歴を完全トレーサビリティ化し、食品の安全性と信頼性を保証。
2025年農業基本法の新機軸
2025年に改正された農業基本法では、農業の社会的役割と国の食料安全保障を強化するための新制度が導入されました。
- 農業の公益的価値を憲法に位置付け
- 若手就農者向け「農業起業家ビザ」創設:海外からの若手農業人材受け入れを促進。
- 地域特産品保護制度の拡充:地理的表示(GI)や伝統的生産方法の保護を強化。
消費者が変える農業の未来
農業の変革は生産者だけでなく、消費者の行動変化にも支えられています。
パリ市民を対象とした 「デジタル農民」プロジェクト では、約10万人が仮想農場をオンライン運営。参加者の75%が地産地消を実践するようになり、CSA(地域支援型農業)への加入者は3倍に増加しました。
これは都市と農村をつなぐ新しいモデルとして注目されています。
ミレニアル世代の購買行動と農業の未来
近年、1980年代から1990年代半ばに生まれたミレニアル世代は、環境や社会に配慮した消費を重視する傾向が顕著になっています。
リヨン国立農学研究所の調査によれば、その購買行動は以下のように特徴づけられます。
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 有機認証製品購入率 | 68% |
| 地元生産者直接取引 | 53% |
| 食品ロス削減意識 | 89% |
| 持続可能包装重視 | 74% |
これらの数値は、ミレニアル世代が単に価格や利便性だけでなく、環境保護・地域経済の支援・資源の有効活用を購買判断の重要な基準としていることを示しています。
特に食品ロス削減への関心の高さ(89%)は、農産物の流通や販売方法にも影響を与えつつあります。
関係性の再構築こそが鍵
リヨン国立農学研究所のアンヌ・デュボア教授は、持続可能な農業の未来についてこう語ります。
「真の改革は技術革新だけでは実現しません。必要なのは、生産者と消費者、都市と農村、そして伝統と革新をつなぐ“関係性”の再構築です。この架け橋こそが農業の未来を拓くのです。」
つまり、環境対応型農業や新技術の導入だけでなく、人と人、地域と地域をつなぐ仕組み作りが、持続可能な食料システムには不可欠だということです。
国際農業見本市(SIA)で見えた希望
2025年度の国際農業見本市(Salon International de l’Agriculture)にはマクロン大統領も姿を見せましたが、会場で最も話題になったのは、農家出身のフランソワ・バイルー首相の行動でした。
バイルー首相は会場に12時間滞在し、農業者一人ひとりの声に耳を傾け、現場の課題や要望を直接聞き取ったのです。この姿勢は農家から大きな信頼を集め、「政府が本当に農家の立場に立って考えている」との印象を与えました。
農家にとっての変わらぬ舞台
EU全体では依然として厳しい経済・規制環境が続きますが、フランスにおいて国際農業見本市は、農家が政府や国民に対して率直に意見を伝えられる貴重な発信の場であり続けています。
この場が今後も変わらず維持され、農業の現場の声が政策や社会に反映されることが、持続可能で活力あるフランス農業の再生には欠かせません。

残念だけど、農家の人たちが苦しんでいる問題の多くはEUが制定した共通農業政策が原因となっていて、マクロン大統領やバイルー首相にいくら不満をぶつけても、彼らにできることは限られているんだ、それは農家側もわかっている。1962年から実施されている共通農業政策(CAP)はもともと、安定した収入と持続可能な農業の両立を図るための制度で、開始当初は、価格保証や補助金制度を通じて農業生産を大幅に増やすことに成功した。かつては食料不足が深刻だったヨーロッパが、わずか数十年で“食料輸出国”の仲間入りを果たせたのは、CAPのおかげだったんだ。しかし時代が変わり、かつての成功モデルは今や加盟国の足かせになっている。すべての国に共通の政策を当てはめることが難しくなっている最大の理由は、環境問題と気候変動の深刻化だ。規制強化に反対する国は主に南欧に多く、干ばつや山火事、そして猛暑の被害に毎年のように苦しめられていて、農家が気候変動の最前線にいる。最近では水不足のために地域の住民と水を巡る対立や裁判なども起きていて、環境改善どころじゃない状況だ。北欧が環境重視なのは「理念主導型」で、自然との共生や持続可能性が国民意識に深く根付いているからだし、東欧の場合は「制度・経済インセンティブ型」で、EUの補助金を受け取るためには、EUが定める環境基準を守る必要があり、その達成が経済的な利益に直結するためだ。国ごとに事情や優先順位がまったく異なるため、政策議論では焦点がかみ合わず、しかも気候や環境問題の状況は年々悪化しており、先が見えない。
EUの目指している理想が正しいことは誰もがわかっている。農薬や化学肥料の使用を制限して、有機農業を推進する、動物福祉基準を強化して、家畜に優しい「畜産」や「酪農」を目指す、自然環境を尊重し、環境と生態系を守りながら、環境に優しい農業を目指す。それは全ての国が目指すべき農業の最終形態だと思う。だからといって猛暑のなか水も不足し、高齢なうえ人手も足りない農家にこれ以上どう努力しろというのか。27のEU加盟国の農家全てを有機農業に転換させるなどという壮大な目標を達成するためには、時間も膨大な資金もかかる。その準備ができていないのに、規制の強化から始めるなんて無謀すぎるよ。
従来の農業から有機農業に移行するのは、堆肥づくりなど新たな仕事が増え、肉体面の負担が大きくなる。しかし若い人が減るいっぽうでは担える人がいない。どんなに頑張っても補助金がなくては続けていけないような職業に就きたい若者など少ないだろう。
フランスの農家たちも苦労してEUの規制を守った結果(守らざるを得ない)、生産コストが高くなり、農作物の価格が高騰して、市民が購入できる値段ではなくなってしまった。例えばEUの規制に縛られないモロッコから輸入したトマトに比べると、フランス産のトマトは3倍近く高くなっている。ロシアのウクライナ侵攻後の物価高に苦しむ市民にとって地域の野菜は高嶺の花となり、EU圏外の安い輸入野菜を購入するしかなくなった。需要増から農産物の輸入量が増え、結果的にフランス産の農産物は、スーパーやマルシェで見かけることが少なくなった。高すぎるという苦情が出て売れないからね。そのため去年のデモでは、高速道路を占拠したトラクターが一斉に、道路に売れ残ったトマトをぶちまけて抗議したんだ。時間とともに潰れていく大量のトマトが首都高速を真っ赤に染めて、血を流しているようで、農家が味わっている苦しみそのものを映すメタファーのように見えた。
農家にとって大切に育てた作物を処分するほど辛いことはないし、値段だって上げたくないけど、それしか生き残る方法はないし、EUにだって輸入農産物との価格差を解消するほどの補助金までは出せない。でもわざわざ遠くの国から農産物を輸入して消費させるなんて、二酸化炭素の削減目標からも大きく逸脱することになり、自ら環境を悪化させていることに気づいていないはずがない。
作地面積を減らさせて農薬や肥料の使用を制限すれば、農産物が減収して価格が高騰することは当然予測できたはずなのに、農産物の高騰により市民の不満が高まると、農家へのサポートは後回しにして、南米の4カ国との間に(アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイ)メルコスール貿易協定を結んで、安価だけれども危険性の高い輸入野菜や輸入果物の関税を撤廃して安く仕入れられる協定に署名してしまったんだ。メルコスール貿易協定では南米からの農産物の関税撤廃の見返りとして、EU各国からの特定の製品の関税も撤廃された。ワインに対する最大35%の関税が撤廃されたり、工業製品や自動車、化学製品、製薬品、テキスタイル、繊維製品などに対する関税も段階的に廃止されることが決まった。でも関税が撤廃される品目に対して、フランスでは元国営企業である自動車会社のルノーと、ワイン&スピリッツやファッション、宝飾品などを扱う世界最大級のラグジュアリー・コングロマリットであるLVMHに対する忖度が噂されているんだ。実際にルノーはEU圏外への輸出が伸び悩んでいるし、LVMHの寄与はフランス経済にとって重要で、LVMHの多額の寄付金と協賛がなかったらパリ・オリンピックは実現しなかったと言われるくらい政府にとっても頼みの綱だ。農産物も工業製品の輸出も停滞しているなか、高級品の関税撤廃で輸出を引っ張っていってもらいたいというのもわかる。だけどそのために農業が犠牲になるとしたら国民は納得しないだろう。これでは農民を締め付けて貴族に富が流れる、フランス革命前の状況に近づいていってしまうよ。
安全面に関しても、南米は農薬や肥料の規制が緩く、欧州で以前から規制されているネオニコチノイド系の殺虫剤の使用が許可されている。この農薬は生育段階で使用しなくても、輸入された野菜や果実を洗うことにより下水から土壌汚染をしてしまうので、EUがいくら農薬を規制しても意味がなくなってしまう。ネオニコチノイド系の殺虫剤の悪影響は多岐に渡り、害虫だけでなくミツバチも殺してしまうことから蜂蜜の生産量が大幅に減少し、養蜂家や消費者団体が声を上げたことでヨーロッパ諸国では使用禁止になったんだ。殺虫剤が蜂に直接当たらなくても、植物が土から吸収することで花粉や蜜に移行し、ミツバチがそれらを摂取することで神経系に悪影響を及ぼすほど強力な農薬なんだ。
EUでは禁止しているネオニコチノイド系の農薬を、輸入品に対しては許可してしまう、そんな矛盾を続けていたらEUの農業が本当に破綻してしまうよ。
農業人口が減って(無理もないよ)、未来の農業はデジタルに頼るしか存続する方法はないことは農家も覚悟しているけれど、恐ろしいのは、またEUが必要もないのにデジタル化に介入してきて、規制で縛って発展を阻んでしまうのではないかということだ。
唯一の希望は、去年の末に首相に就任したフランソワ・バイルー首相だ。バイルー氏は学校を出た後に教員になったものの、酪農家を営んでいた父親が事故で亡くなり、教員の勤務のかたわら農家の仕事をしていたという経歴の持ち主だ。彼の農家は15ヘクタール未満の家族経営で、飼育していた牛は17頭という比較的小規模農家だったことから、農家の大変さや置かれている状況は痛いほど理解していて、今年の農業見本市では12時間も滞在して、農家の人たちの話を聞き続けたんだ。もちろんフランス一国だけでEUの規制を変えさせることは難しい。でも政府が農家側についてくれることで、何度でも説得してくれる希望はあるし、新たな技術やシステムの導入により少しでも状況が改善できるもしれない。
フランスは、EUの規制に縛られてから、転がるように世界の農業国としてのポジションから転落してしまい、今やフランスの未来に農業は生き残っているだろうか?と懸念されるほど危機的な状態にあるけど、毎年の大規模な農業見本市が残っているおかげで、農家が直接政治家に発言できる機会があることが救いだし、国民も農家に対するリスペクトがある。去年のデモでは、約7万2千人の農民が全国で抗議デモを行い、4万1千台ものトラクターが動員された。約6,500人の農民と約4,500台のトラクターが主要道路を封鎖したせいで首都圏への流通が停滞し、生鮮食料品が店から消え、渋滞が続いて首都が麻痺する事態が2週間近くも続いたんだ。それでもデモを続ける農民たちに対して文句を言う市民はいなかった。それどころか夜を徹して高速道路を閉鎖する農民たちに差し入れをしたり、家のシャワーを使ってくれるよう申し出たりしてデモを応援したんだ。市民たちは農民たちを応援することでデモに参加していたんだね。そのため政府も強行手段を使って取り締まることができず、農民たちがスローガンにしていた、暴力を使わず負傷者をひとりも出さない静かなデモが実現したんだ。信念を持った市民の団結が政府にとっては一番手強いから。市民の団結がフランス革命となり、国の歴史を変えたフランス人の心意気は今も続いていたんだね。
関係ないけど、2月の夜は寒いから農民たちが高速道路の上で焚き火をして暖を取りながら、簡単なバーベキュー台を設置して、パリに入れず廃棄処分になってしまう野菜や肉を焼いて、ワインと一緒に皆に振る舞っている映像がニュースで流れたんだ。庶民には手が届かなくなったフランス産の野菜や肉だ。それまで冷静にニュースを読んでいたニュースキャスターが思わず「わあ、これは美味そうだ!」と素の感想を漏らしていたのが面白かった。高速道路と焚き火と季節外れのバーベキュー。シュールで素朴で人間味に溢れていて、ニュースを見てバーベキューがしたくなった人は多かったと思うし、特に子どもたちには強い印象が残っただろうね。食べることってやっぱり説得力があって、意図せずに最高の広告になったよね。
今年の農業見本市では、去年の失策を踏まえて開催前に農民代表と政府が落ち着いて、活発なディスカッションを交わし、法の改正も約束されたことで農家の怒りのガス抜きができたと言われている。(農家の怒りはそう簡単には収まらないけれども、それは当然だろう。)
農家も市民も政府も、皆がフランスの農業を守るために前向きに考えているんだから、EUはこれ以上規制を増やさずにまずは見守って、加盟国を指導するのではなく後方支援に回るべきだと思うんだ。世界に誇る農業国の農家数が急減し(特に2010年から2020年の10年間で農場数が約21%も減少しているんだ)、状況が悪化しているのはEUの他の国々も一緒だということを真摯に受け止めてほしい。手遅れになる前に、無用な規制や条約は撤廃しようよ。貿易外交のコマとして農作物を利用するな!と言いたいよ。
植物も家畜も生きものだから(魚だってそうだ)、気候変動には特に大きな影響を受けてしまう。不作による食糧不足や値上がりなどはこれから世界中で深刻になっていくと思うし、根本的な対策を見つけるのはとても難しいことで、一朝一夕に成し遂げられることではないと思う。
だからといって輸入によって食糧不足や値上がりを解決することは、一番手っ取り早いけれども自国の農業が、もしかすると輸出国の環境も犠牲になる可能性もある両刃の剣であることを忘れてはいけないと思うんだ。
特に貿易協定などを安易に結んでしまうと、一時的なはずの解決策に長い間縛られて、後で後悔することになる。EUの失敗から学んで日本の政府も慎重に、日本の農業を長期的な視点で大切に育てていってほしいんだ。フランスの国際農業見本市が掲げるように、『農業は国の誇り』なんだから。