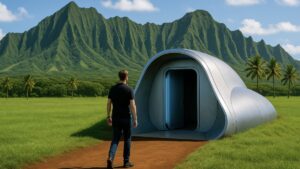攻撃ドローンの台頭と脅威
近年、戦場におけるドローンの役割は急速に拡大しています。特に、安価な攻撃ドローンの普及は、戦争のあり方を大きく変えています。
例えば、ロシアとウクライナの紛争では、Shahed-136やGeran-2といった一方通行の攻撃ドローンが自爆型や武装ドローンとして大量に使用されており、アメリカ軍も中東地域で攻撃ドローンを運用しています。
主な攻撃ドローンの種類
自爆型ドローン
ロシアがウクライナで使用しているとされるイラン製のShahed-136や、その類似品であるGeran-2が低価格の自爆型ドローンの例です。
これらの攻撃ドローンの主な特徴は以下の通りです。
- 低コストであること。これにより、大量に投入されることが可能となり、敵の防空システムに飽和攻撃をかけることができます。
- 遠隔操作または自律航行が可能であること。
- 目標に自爆することで損害を与えることにより、「カミカゼドローン」とも呼ばれています。
武装ドローン
武装ドローンとは、武器を搭載し、攻撃能力を持つ無人航空機(ドローン)を指します。
具体的には、以下の2種類の武装ドローンが存在します。
- 攻撃型武装ドローン(自爆型ドローンを含む):
目標に対して自ら攻撃を行う能力を持つドローンで、特に低コストな自爆型ドローン(MTO – 遠隔操作される弾薬)Shahed-136や、その類似品であるGeran-2は、このタイプの代表的な例です。 - 防衛型武装ドローン(対ドローン迎撃ドローン):
他のドローンを空中で迎撃・破壊するために武器を搭載したドローンです。
武装ドローンという言葉は、攻撃を行うドローンと防御のために武器を搭載したドローンの両方を指す可能性があります。特に低コストな攻撃ドローンの脅威と、それに対抗するための低コストな防衛型武装ドローンの開発動向が注目されています。
ドローン群(スウォーム戦術)
- 「ドローンスウォーム」とは、少なくとも3機以上、場合によっては数千機のドローンが連携し、最小限の人間の介入で任務を遂行できるシステムを指します。これは、生物界で見られるアリやハチ、鳥の群れの動きにヒントを得た「群知能(Swarm Intelligence)」を活用しています。
- 現代のドローンスウォームは、人工知能(AI)や機械学習(ML)を統合し、GPSジャミングや電波妨害、悪天候といった障害を克服しながら、協調した行動を維持します。制御方法は、事前にプログラムされた飛行経路、地上の司令部からの集中管理、ドローン同士のリアルタイム通信による分散型制御など、多岐にわたります。
- 低コストなドローンを大量に投入することにより、敵の防空システムを飽和させ、迎撃を困難にする戦術をスウォーム戦術と呼びます。
ロシアがウクライナで使用しているShahed-136などの低コストな自爆型ドローン(MTO)が大量に投入される状況が、スウォーム戦術です。
ドローンスウォームは、軍事戦略のコストと効果のバランスを大きく変えました。
空・陸・海の複数の領域で同時に作戦を展開できるため、戦場の状況をリアルタイムで把握しながら、敵の防御を突破し、精密攻撃を実行することができます。
大量のドローンを集中して送り込むため、敵の防衛システムを消耗させる効果もあります。
コストの不均衡
攻撃ドローンの増加に伴い、各国は迎撃手段の開発を進めていますが、迎撃用のミサイルには攻撃ドローンよりも高度な技術を要するため、防衛側はコストの高い迎撃ミサイルを使用せざるを得ず、攻撃側にとって有利な経済的構造が生まれています。
例えば、数千ドルのドローンを迎撃するために、数十万ドルのミサイルを使用するのは非効率であり、「コストの不均衡」という問題が浮上しています。
低コストで効果的な防空システム
この課題に対応するため、エアバスは無人航空機システム(UAS)を防衛の重要装備と位置付け、対ドローン防衛に特化したLOAD(Low-Cost Air Defense)という低コストの防空ドローンを開発しました。LOADは、増え続ける低コストドローンの脅威に対し、より経済的で効果的な防衛手段を提供することを目的としています。
LOADの主な特徴
- 低コスト:
高価な迎撃ミサイルと比較して、運用コストを大幅に削減することが期待されています。ベースとなっているのが既存の標的ドローンDo-DT25であることも、低コスト化に寄与しています。 - 再利用可能:
パラシュートによる回収オプションを備えており、機体の一部を再利用することで、さらなるコスト削減を目指しています。 - 武装:
2~3基の小型空対空ミサイルを搭載し、複数のドローンを同時に攻撃できる可能性があります。ヨーロッパ製の低コストミサイル(MBDA EnforcerやThales Martletなど)が候補として挙げられています。 - 自律性:
AIを活用し、自律的な運用が想定されており、人的リソースの負担を軽減することが期待されます。 - ITARフリー:
アメリカの国際武器取引規則(ITAR)の適用を受けないため、ヨーロッパ各国はアメリカの許可なしにこのシステムを導入・運用できるという利点があります。これは、ヨーロッパの軍事的自立性を高める上で重要な要素となります。 - 配備予定:
2027年の実用化を目指しており、近い将来の実戦投入が期待されています。
仕様と性能
「LOAD」は、エアバスの「Do-DT25」標的ドローンを改良したもので、再利用可能な設計となっています。この無人機は自律的に敵のドローンを探知し、オペレーターの監視と許可のもとで迎撃する仕組みです。下は、Do-DT25を元にした仕様予想です。
- 全長:3.1メートル
- 翼幅:2.5メートル
- 最高速度:300ノット(約555km/h)
- 作戦範囲:約100km
- カタパルト発射方式
- パラシュートで着陸し再利用可能
このシステムは、レーダーのカバー範囲を補完し、防空の隙間を埋める役割も果たします。
ミサイル搭載
LOAD(Low-Cost Air Defense)は、ミサイルを搭載して他のドローンを無力化することを目的としたシステムです。
ミサイル搭載は、航空機やドローンに攻撃能力を付与する重要な手段です。
- LOADは、最大3基の空対空ミサイルを搭載し、レーダーなどの情報に基づいて、自爆型ドローン(MTO – munition téléopérée)などの敵ドローンを追跡、検知、破壊する能力を持ちます。
- エアバスは低コストなヨーロッパ製のソリューションを示唆しており、MBDAドイツのEnforcer SADM(Small Anti Drone Missile)やタレスのMartletなどが例として挙げられています。これは、LOADとは異なるアプローチで、より多様な脅威に対応できる可能性が示唆されています。
また、ミサイル搭載という観点とは違うものの、低コストな対ドローン手段として、誘導キット付きの無誘導ロケット弾(Hydraなど)を空対空で使用するアイデアも検討されています。これは、ミサイルよりもさらに低コストでドローンなどの脅威に対処する方法として注目されています。
再利用可能性
エアバスが開発したLOAD(Low-Cost Air Defense)は、重要な特徴の一つとして「再利用可能」であることが挙げられています。
- 安価な攻撃ドローンが大量に投入される現代の戦場において、迎撃側もまた低コストで持続可能な防衛手段を持つことが重要です。
- 再利用可能なドローンは、初期投資は必要であるものの、長期的な運用コストを抑えることが期待できます。
- 完全な再利用ではないものの、機体の一部を回収して再利用することで、製造コストや資源の節約につながります。
- これは、使い捨てが前提となる一方通行の攻撃ドローンとは対照的な設計思想です。
再利用可能なドローンの意義は、防衛戦略と経済性のバランスに大きく関わってきます。再利用可能性は、単に低コストであるだけでなく、持続的な運用を見据えた設計であることがわかります。再利用可能なドローンは、将来の防衛戦略において、経済的かつ効果的なソリューションとして重要な役割を果たす可能性があります。
攻撃ドローンの現状と展望
また、LOADはヨーロッパの軍事的自立性の強化にも寄与します。ITARフリー(米国の武器輸出規制の対象外)であるため、アメリカの許可を必要とせず、ヨーロッパ各国が独自に導入・運用できる戦略的な柔軟性を持っています。
現代の安全保障においては、高価な軍事技術だけでなく、コスト効率に優れたソリューションも重要な役割を果たします。エアバスのLOADは、まさにその一例と言えますね。