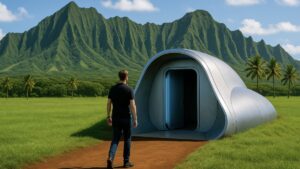経済安全保障リスクの正体
レアアースの供給は、特定の国に大きく依存しています。ここが、今いちばんの弱点です。
- 中国への依存:世界のレアアース供給の約7割を中国が握っています。
- 重希土類の独占:モーターの耐熱性を上げるジスプロシウムやテルビウムなど“重希土類”の生産は、ほぼ中国の独壇場です。
- 輸出規制の衝撃:過去にはトランプ関税に対抗する中国の輸出規制によりスズキの小型車が生産停止に追い込まれたこともありました。資源が突然止まる―これこそ経済安全保障リスクの現実です。
- 中長期の需給ギャップ:永久磁石の需要はこの10年で約3倍に。ネオジム、プラセオジウム、ジスプロシウム、テルビウムの使用量は2035年に176,000トンへ。現状の計画だと約30%(6万トン)不足と見込まれます。
つまり、地政学と需給がダブルで効いて、価格変動リスクも大きくなる、というわけです。
それでも前に進むなら―リサイクルは“今すぐ”の解
EVの普及、風力発電、省エネ家電の拡大で、レアアース需要はまだ増えます。資源の偏在や環境負荷を考えると、リサイクルは喫緊の課題です。ところが現実は厳しく、レアアースのリサイクル率は1%未満。理由はシンプルで、従来法が手間とコストの塊だったからです。
- モーターを分解
- 350〜500℃で熱脱磁
- 強力な磁石を安全に取り外し
1台に2時間以上。これでは広がりません。
日本から出てきた“逆転の発想”①:モーターごと溶かす
ここで登場するのが、日産自動車×早稲田大学の共同開発。発想は痛快です。
「分解しない。脱磁もしない。丸ごと溶かす。」
やることはこうです。モーターを炭素材や鉄、ホウ酸塩系のフラックスと一緒に炉へ。1,400℃以上で一気に溶かすと、重い鉄合金層と、レアアースを含む溶融酸化物(スラグ)層の二層に自然分離します。上の からレアアースを回収する、というシンプルな流れです。
- 回収率:98%
- 作業時間:約50%短縮(分解・脱磁が不要)
- 大量処理にもフィット
日本から出てきた“逆転の発想”②:そもそも使わない
もうひとつの挑戦は、非レアアース化です。京都のベンチャー、ネクストコアテクノロジーズが開発したのは、「ヘルメット」と呼ばれる0.03mmの極薄金属帯。これをモーターに使うと発熱がぐっと抑えられて、重希土類の添加が不要になります。
- 資源リスクの解消:輸出規制の“切り札”だった重希土類から卒業
- 省エネ:消費電力を最大50%削減のポテンシャル(=航続距離アップの期待)
- 産業インパクト:すでに国内外の自動車・家電メーカー約30社がテスト中
日産は、そもそも磁石を使わないモーター(アリアなど)にも踏み出しています。リサイクルと非レアアース化、両輪で依存を下げるのが今の日本の戦略です。
どう変わる? サプライチェーンの新たな未来
非レアアース技術は、サプライチェーンの常識そのものに挑戦します。
- 依存の脱却:重希土類なしで耐熱をクリア → 地政学リスクを回避
- 価格の安定:希少資源に引っ張られない分、コスト変動が緩和
- 性能の底上げ:発熱抑制=効率アップで、ユーザー体験も改善
- スピード感:新規鉱山を待つより、リサイクル&非REE化のほうが早く供給に寄与
結論―2つの道が、同じ場所に向かっている
- リサイクルで取り戻す(日産×早稲田の“丸ごと溶かす”方式)
- 依存しない設計に変える(ネクストコアの“使わない”方式+日産の無磁石モーター)
どちらも目指すのは、資源偏在に振り回されない未来です。資源・環境・経済・地政学――四つ巴の課題に対して、日本は“現場で効く”解を出し始めています。
次の10年、EVの地図は塗り替わります。中心にあるのは日本発の、常識をひっくり返すシンプルなアイデアです。
資料:2022年の、学術講演会発表 (“環境資源工学”/学会発表資料)

日産に関して心が動くようなニュースを聞くのは、もう何年ぶりだろう。これまでの見出しはどれも暗いものばかりだった。工場閉鎖、淘汰されるラインナップ、縮小による生き残り戦略の話。まるで、静かに消えていくのを待っている会社のように思えた。ところが、胸が踊るような研究結果が公表された。逆風の中でも、「技術の日産」の魂は生き続けていたんだ。
いま世界がやかましく話しているのは、レアアースのことだ。レアアースは現代生活の“見えない骨”―スマートフォンの中に、電気自動車を走らせる強力なモーターの中にある。そしてこのレアアース問題は、日本だけの問題じゃない。世界中の問題だ。資源の問題であると同時に、地政学の問題でもある。供給のほぼ4分の3は中国から来ている。つまり、北京がデトロイトも、愛知も、シュトゥットガルトも―どこであっても製造業者の運命を握っているのだ。無関係な国や人はいない。アメリカはなおさら痛切に感じているに違いない。強気に出たい国なのに、相手は「レアアース」という切り札を握っている。関税戦争は繰り返されても、他の国がとばっちりを受け、中国自身はほとんど傷つかない―そんな構図だ。
だからこそ日産の動きに目を奪われた。世界がまた日産に注目する日が来るかも知れない。磁石に頼らないモーター、アリアというクロスオーバーには、電磁励磁同期モーター(EESM)が積まれている。レアアース磁石の代わりに銅線のコイルで磁場を作る方式だ。ネオジムも、ジスプロシウムも、そうした重希土は不要。つまり、自動車メーカーを中国に縛りつけていた鎖が外れる。平たく言えば、「資源の鎖から自由になる未来」が実現するかもしれないんだ。
そして日産はそれだけでは終わらない。使った分を返す道も歩いている。長いあいだ重希土の使用量を減らしてきた歴史がある。今は大学と組み、使用済みモーターからレアアースを効率的に取り戻すリサイクルプロセスを試験中で、驚くほど高い回収率が出ている。ショールームで自慢できる派手な機能ではない。だが、業界が安心して生産活動を続けていくためには、こうした静かな基盤作りが必要なんだ。地味に見えても、ゲームをひっくり返す力を持つ革新だ。
もちろん、簡単な話ではない。中国が輸出管理を強めれば、生産計画はすぐに揺らぐ。調達は今も綱引きのまま。それでも、磁石フリーの駆動方式と、掘り出した資源を循環させる仕組み―「攻め」と「守り」を両方そろえれば、嵐の中でも切れるカードを持っているような安心感がある。
アメリカは自国で鉱山や磁石工場を再建しようと急いでいる。けれども精製となると、中国の優位はまだ揺るがない。だからこそ、日産の三拍子―「使わない/減らす/戻す」―は、やがて業界全体の合言葉になるだろう。
ぼくは日産にこの道を歩き続けてほしい。派手な一発を狙うのではなく、基盤をひとつひとつ更新しながら、“縁の下の力持ち”となり業界を支える役目は、今の日産が担ってこそ説得力があると思う。
そして一日も早くかつての輝きを取り戻し、ブルーバードやスカイライン、フェアレディZやGT-Rのような名車で、ぼくらをまた驚かせてほしいんだ。