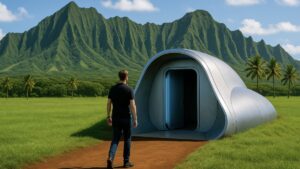収穫(ヴァンダンジュ)は、なぜどんどん早まるのか?
フランス・ブルゴーニュ地方のボーヌには、1659年から続く「収穫日記録」が残っています。そのデータによると、地球温暖化が加速した1988年以降、平均で16日も収穫が前倒しになっています。
理由はシンプルです。気温が高くなると芽吹きから開花、成熟までのサイクルが一気に進むから。糖度が高まり、アルコール度数も自然と上がります。生産者は「早摘み」で帳尻を合わせますが、限界があります。2019年の南仏では熱波で葉も果房も炭化するほど日焼けし、ガールやエローの一部では収穫の半分を失うほどの被害になりました。
2025年の夏:北は追い風、南は逆風
2025年の6/1–8/17はフランスで観測史上3番目の暑さとなりました。それでも生産量は総じて上向きで、北半分(ロワール、ブルゴーニュなど)では温暖化により「ちょうどよい成熟帯」に近づいたため、果実の完熟=品質向上が起きやすくなっています。かつて必要だった補糖*が不要なほど成熟が良好で、甘くなっているのです。
逆に南仏では状況が厳しく、アルコール度数は30年前の11.8度から14度前後へ。酸は下がり、味わいは重くなりがちです。消費者が求める“軽やかでフレッシュ”なトレンドと逆行してしまい、市場の立場は厳しくなっています。
*補糖(chaptalisation)
醗酵前の果汁に砂糖を加え、潜在アルコール度を補う伝統的手法。EU法では条件付きで認められますが、温暖化後は北の産地でも必要性が下がる傾向です。
甘さは“力”だが、過ぎれば刃
気温上昇で糖度の上がった果汁は、当然アルコールを引き上げます。ラングドックで1984~2013年の大量サンプルを追った研究では、潜在アルコールが+2%超、総酸は約1g/L低下という傾向が確認されました。味の輪郭(酸)を保ちながら、熟度(糖)をどう抑えることができるか。いまのフランスワインの核心は、そこにあります。
アルコール感が上がり、味は甘く重くなっていくなか、トレンドは“軽やかでフレッシュ”。
消費者も、温暖化により食の嗜好が変化しています。気温も湿度も高い日が多くなり、軽く冷たい食事が多くなり、それに合わせるワインも、軽やかで低アルコールの飲みやすいワインが好まれる傾向にあります。
世界のワイン消費は2024年に過去60年で最低水準まで落ち込んでいます – 量より質・価格感度の高まりで、日常酒の競争はよりシビアに。生産側は“暑さに強く、軽く、おいしいワインづくり”という難題と向き合っています。
市場の壁は気候だけじゃない
フランス国内でも飲酒量は減少中。さらにアメリカはEU産ワインに15%の関税を上乗せしました。市場と気候、二つの大波が同時に押し寄せているのです。
国の補助金で「抜根(アラシャージュ)」キャンペーンも実施されていますが、ぶどうを抜いたところで長期的な展望が描けるわけではありません。現場の栽培家からは「補助金だけでは救われない」という声も聞こえます。
現場の負荷も増大です。炎天下の畑作業は体力・メンタルの両面に響き、「5年以内にこの仕事を離れるかもしれない」と答えたワイン産業従事者は43%に達するという調査も。気候対応は“人を守る農”でもあります。
畑で働く人にも限界が – 労働安全・雇用の課題
収穫のピークが真夏に移動したため、炎天下での長時間労働が常態化しているのです。現場では、早朝や夜間収穫、送風機、可搬式シェード、ミスト散布などの工夫でなんとか人を守ろうとしています。
ぶどう栽培は猛暑に極めて弱い職種です。建設業に次ぐレベルで熱ストレスの影響を受けると指摘されます。
熱中症・脱水・睡眠不足・精神的負担が重なり、収穫の早まりで真夏の長期労働”が常態化しているのが実情です。
アルザス、エギスハイムの家族経営ワイン農家では、2025年の収穫開始が200年の記録で最速となり、酸は十分で“ガード向き(熟成向き)”と胸をなで下ろす一方、40℃の炎天下で4〜5週間作業が続く現実に不安を隠せません。
従業員や手伝ってくれる人々の健康状態も考慮しなければならず、「私の世代が、最後に“安定して暮らせる”アルザスの栽培家になるかもしれない」と語っています。
品種のシフトチェンジ
温暖化への対応として、品種の見直しが進んでいます。
- ボルドーでは暑さに弱いメルローを減らし、耐暑性のあるカベルネ・ソーヴィニヨンを増やしています。さらに6種類の新しい品種が「補助的品種」として正式に承認されました。
- ブルゴーニュでは「ピノ・ノワール」を替えるわけにはいかないため、収穫時期や樹冠管理で調整しています。
- ラングドックではギリシャの「アシルティコ」を試験導入。高温でも酸が残りやすい品種ですが、AOPの規定により導入には制限があります。
畝の並べ方も見直されています。東西に並べるのではなく南北に植えることで、午後の西日のダメージを軽減する。遮光、被覆、樹冠管理 – “焼かせない”ための畑の管理は、醸造というより造園設計に近づいています。
ぶどう畑 × 人工衛星
いまフランスで注目されているのが、人工衛星データを使った“精密ヴィティカルチャー”です。
欧州のSentinel-2衛星が観測するマルチスペクトル画像から、畑ごとの樹勢マップや水分ストレスを解析。どの区画を先に収穫するか、どこに灌漑を入れるかを俯瞰して判断できます。
オクシタニー地方では、現地での水分測定データと衛星画像を組み合わせてAI解析し、畑スケールで水ストレスを可視化する実証も進んでいます。伝統的な「経験と勘」に加えて、「宇宙からのまなざし」がワインづくりに加わったのです。
未来に向けた選択肢
気候変動は、ワイン産地を「北へ」押し上げています。しかし単純に勝ち負けの話ではなく、畑ごとの適応策が未来を決めます。
これからのぶどう畑が取り組むのは、こんな戦略です。
- 畝の方向を見直し、葉の量で日射をコントロール
- 被覆作物やワラ敷きで土壌の水分を保持
- 区画ごとに収穫や仕込みを分けて調整
- 耐暑・耐乾の品種や台木の導入
- 夜間収穫や可搬式シェードで人を守る
- 衛星やドローンで“畑の状態”を見える化
- 低アルコールで爽やかな新しいキュヴェを提案
200年の収穫日記と、最新の人工衛星マップ。伝統とテクノロジーが同じ未来を指し示すのは、偶然ではありません。
フランスワインはこれから「テロワールの記憶」だけでなく、「気候変動の記録」も味に刻み込んでいくのかもしれません。

ぼくも学生のころ、収穫(ヴァンダンジュ)に参加したことがある。フランスには学生ができるアルバイトが限られているからね。日本ではバイトの主流と言える飲食業や販売業は、こちらではプロの世界で、アルバイトを雇う店などそんなにない。カフェのギャルソンなんて、40から50代のムッシュたちが誇りを持ってキビキビとしごとをしていて、学生の分際で真似できるような職業ではないからね。1週間から2週間、収穫のお手伝いをしながら宿代を節約して(雑魚寝ではあるけど)、旅をしながら帰ってこられる収穫のしごとは学生にとっては理想的なアルバイトに思えた。でもフランス人はどれほど大変な作業かを知っているから、集まるのは外国人の学生ばかりだったな。ぼくも1日目でもう無理だ!というくらいボロボロに疲れて、いくら飲んでもいいと言われていたワインも殆ど飲まずに、毎晩倒れるように寝ていたことを覚えている。いい人たちばかりで良い思い出にはなったけど、一度でじゅうぶんだと思ったね。
でもその頃はぶどうの収穫といえば秋だったから、朝・晩は寒いくらいで、日中でも25度以下だったと思う。それでも日差しは強いし、重装備で(畑のしごとは何でもそうだけど、虫やヘビも出るし、ぶどうの枝はかなり鋭くて当たったり踏んだりして怪我をすることもあるから、帽子、長袖、長靴は必須だ)、背中に、ホットと呼ばれる摘んだぶどうを放り込む籐かごを背負って、ちょっと歩くだけでも汗だくになった。いま、夏の最中に気温が40度近くで同じような装備で作業するなんて、想像もできないよ。2時間も続けたらぶっ倒れちゃうんじゃないだろうか。
いくら仕事でも、そんな危険なことは止めるべきだよ。暑さに強い品種は開発できるとしても、人がその環境で仕事をするのはどう工夫しても無理がある。
もうね、収穫用のロボットに任せるしかないと思うんだ。今のロボットは、果実を傷つけたり潰すことなく、圧力を変化させて上手に摘むことができるし、熟成度を確認するのも人間より正確だったりする。ロボットに人の代わりをさせるとなると、いろいろな反対意見も多いけど(人の手で摘んでこそ高級ワインだ、とか言う人がいるけど、摘んだのがロボットか人間かで味に違いなんて出るはずがない、そんなエモーショナルなことを言っている場合じゃないんだ)これはもう人命救助の領域だよ。全ての仕事をロボットに任せる必要はないけど、人にとって危険な仕事や辛い仕事は少しでも早くロボットに任せていくべきだと思う。もちろん小さな農家ではロボットなんて高すぎて購入できないというところが殆どだと思う。でもこれは、セキュリティ・ソシャル(健康保険や労災保険)なども援助して、これこそ補助金を出すべきだと思うんだ。この猛暑が、これから改善されていく見込みはほぼないし、健康を害する人が続出して、フランスのワイン農家がどんどん消えていってしまってからでは遅いから。