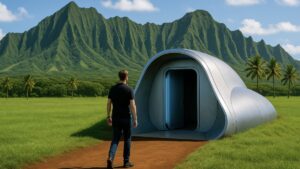ユネスコ無形文化遺産登録がもたらした日本酒の新たな波
2023年12月、日本酒はユネスコの無形文化遺産に登録されました。
原材料はとてもシンプルで、水と米、そして発酵を促す麹菌のみ。
しかし、その味わいは驚くほど繊細かつ奥深く、古くから「神々の飲み物」と称されてきました。
「日本酒は、料理の旨味を静かに引き出し、余韻をふくらませてくれる共鳴器のような存在」
そう語るのは、パリ屈指の高級ホテル《ホテル・ド・クリヨン》のシェフ・ソムリエ、グザヴィエ・チュイザ氏。
彼が魅了されているのは、日本酒が持つ“やさしい包容力”です。
たとえば、ヤギのフレッシュチーズのほのかな酸味、春先のアスパラガスの若々しい香り、あるいは生牡蠣のミネラル感、こうした繊細な料理に寄り添い、ワインをも凌ぐマリアージュを生み出す瞬間があるといいます。
中でも彼が心を奪われたのが、「日本酒界のロマネ・コンティ」と称される福島の銘酒《大七(Daishichi)》です。
複雑かつ奥行きのある味わいに感動し、自らのフランス料理のフルコースに自信をもって組み込んでいます。
五感を刺激する日本酒の世界
日本酒の魅力の一つは、その驚くべき多様性にあります。
アルコール度数はおよそ15度前後とやや高めながら、味と香りのバリエーションは実に豊か。
ミネラル感あふれるすっきりタイプ、華やかなフローラル系、熟れたフルーツの香り、スパイシーな後味、香ばしいロースト香、さらにはキリリとした酸味──まさに五感すべてを刺激する世界が広がります。
この幅広い表情が、世界中のソムリエや料理人の創造力をかき立てています。
日本酒の歴史 – 庶民酒から世界の高級品へ
日本酒の歴史は古く、紀元前3世紀頃に「口噛み酒(くちかみざけ)」といって、米を口で噛み砕き唾液で糖化し、自然発酵させる原始的な方法が主流でした。
神事や祭礼と結びつき、「神に捧げる飲み物」としての性格が強かったのが特徴です。
奈良時代(8世紀)には、中央政府に造酒司(さけのつかさ)という酒造専門機関が設置され、宮廷用の酒が制度的に造られました。
この頃から麹(こうじ)を使ってデンプンを糖に変える技術が広まり、より安定した品質の酒が造れるようになります。
平安時代には、貴族文化の広がりとともに甘口で濃厚な「白酒」や「練酒」などが飲まれました。
鎌倉時代になると、諸白造(もろはくづくり)という精米した米と麹をふんだんに使う贅沢な製法が登場し、現代の日本酒に近い酒質が確立されます。
この時期には市街の酒屋も増え、庶民の間でも日本酒が広く楽しまれるようになりました。
江戸時代には日本酒文化の大ブームが起き、上方(大阪・灘・伊丹)で醸された「下り酒」が江戸に大量に運ばれ、ブランド化します。技術的にも、「寒造り」(冬期限定の仕込み)や「火入れ」(加熱殺菌)などが定着し、長期保存や安定供給が可能になりました。
明治時代には、醸造機械や精米機の発達で高精白米が容易に得られるようになり、淡麗で洗練された酒質が普及します。
昭和の時代に入ると、戦時中の米不足で、米以外の原料やアルコール添加による「三倍増醸酒」が広まりましたが、戦後の経済復興とともに純米志向が回復しました。
当時ビールはまだ高級品で、日本酒は手軽な日常酒という位置づけでした。
1870年代から、日本でのビール製造が始まっていましたが、戦争による原料不足と統制経済で、ビールの生産は制限されていました。1949年の統制撤廃後も価格は高く、当時は大びん(633ml)で1本100円前後、これは日雇い労働者の日給の半分近くに相当していたため、日常的に飲めるお酒ではなかったのです。
1970年代以降、「吟醸酒ブーム」や「地酒ブーム」が到来し、地方の小規模蔵が個性ある酒を全国に発信するようになります。
日本酒は、家庭の食卓や居酒屋で気軽に飲まれる庶民の酒として愛され、1973年頃には、日本酒の一人当たり消費量が過去最高に到達しました。
しかし国税庁の統計によると、1973年をピークに日本酒の消費量は減少していきます。その背景には、1960年代後半〜1970年代初頭の、所得倍増計画や外食産業の発展にビールの価格低下が重なり、急速に普及していたことがありました。
1980年代に入ると、ビール会社の積極的な宣伝と流通網の拡大により、ビール消費量が急増します。1983年、サントリーが缶入り「ほろよいチューハイ」などを発売し、低アルコールで甘く飲みやすいRTD(Ready To Drink)系飲料が若者や女性を中心に人気になりました。
カクテルブームやワインブームも都市部で拡大し、「日本酒=おじさんの酒」というイメージが固定化してしまいます。
その後は、若者のアルコール離れや高齢化の影響で清酒の消費量は減少するいっぽうでした。しかし、21世紀に入ると海外で日本食が注目されるようになり、それととともに海外市場が拡大し、日本酒の輸出量増加、そしてユネスコ無形文化遺産登録(2023年)によって世界的な評価も高まりました。
日本酒は、寿司や和食だけでなく、フレンチやモダンキュイジーヌとも驚くほど相性が良く、「ワインに並ぶ食中酒」として扱われるようになったのです。
こうした丁寧な造りが、贈答品や高級料理店でのペアリングに選ばれる理由です。
パリにおける日本酒の再発見:誤解から本物志向へ
いまやフランスでは、日本酒を専門に扱うブティックや、ワインの棚の一角に日本酒が並ぶワインショップも珍しくなくなりました。パリの街角を歩けば、シックなガラス瓶に詰められた大吟醸や純米吟醸が、ワインと肩を並べて鎮座している光景に出会えます。
しかし、こうした光景が当たり前になったのは、つい最近のことです。少し前まで、日本酒をパリで探すとなると、日本食品を扱うアジア系の食材店に足を運ぶしかありませんでした。
問題は、そこにいた店員さんが必ずしも日本酒の専門知識を持っていたわけではないことです。
「どんな料理に合うのか?」「吟醸と大吟醸の違いは?」「どれが飲みやすいのか?」といった質問をしても、納得のいく答えが返ってくることは稀でした。そのため多くのフランス人にとって、日本酒は“どれを選んでいいのかわからない謎の飲み物”だったのです。
“SAKE”という名の別物が広めた誤解
さらに、日本酒に対する誤解が根深く残る理由もありました。特に2000年代初頭まで、パリの低価格帯の日本料理店(多くが日本人以外のアジア人経営の店舗)では、食事の最後にサービスとして「SAKE」と称する酒を出す習慣がありました。
ところがその中身は日本酒ではなく、中国産の高アルコール米焼酎(白酒・バイジュウ)や、安価な蒸留酒に砂糖や香料を加えた甘いリキュールだったのです。
これらはアルコール度数が40度前後もあり、香りも刺激的。日本酒の繊細な香味とはまったく別物です。それにもかかわらず、多くの人が「これが日本のSAKEか!」と信じてしまいました。その結果、多くのフランス人にとって「SAKE=アルコールの強度も香りも強烈な酒」で、そのため食事の最後に消化を助けるために飲む酒であり、食事と一緒に飲むものではない、という誤ったイメージが定着してしまったのです。
日本酒を一度も飲んだことのない人にとっては、この“強烈なサケ”体験が初めての日本酒との出会いとなり、本来のやさしい旨味や米の甘みを知る機会はほとんどありませんでした。これは、日本酒のブランド価値を下げる大きな要因でもありました。
変化をもたらした「本物志向」とプロの知識
しかし、この10年ほどで状況は大きく変わります。フランス国内の一流レストランや星付きシェフが、自らの料理に合わせるために厳選した日本酒をワインリストに載せるようになったのです。
加えて、日本酒専門店が次々とオープンし、ワイン専門店のスタッフやソムリエが日本酒の造りや産地、精米歩合の意味まで学び、ワイン同様に丁寧にお客様へ提案するようになりました。
こうした変化が、フランスにおける日本酒の評価を着実に押し上げ、高級日本酒が違和感なく受け入れられる環境を育てました。現在のパリでは、美食家たちがワインリストを眺めながら「今日はブルゴーニュの白にしようか、それとも純米大吟醸にしようか」と、本気で迷う光景も珍しくありません。
実際、パリの星付きレストランでは、ワインリストの一角に獺祭や他の日本酒銘柄が堂々と並び、グラス単位で提供されることも増えています。たとえば、フォアグラには甘口のワインだけでなく純米大吟醸を合わせ、生牡蠣にはシャンパーニュと並んで冷えた吟醸酒をすすめる、そんな提案が自然に行われるようになったのです。
こうして純米大吟醸や吟醸酒など、味の違いがわかる人も増え、日本酒を“特別な日の選択肢”から“日常の食卓に寄り添う一杯”へと押し広げています。
フランス人が日本酒を選ぶときに重視すること
日本の酒店ではコメの品種や精米歩合について、店員さんに細かく質問することは少ないですが、フランスでは当然のように質問を受けるそうです。
ワインを買うときのように、店員に「どんな食事と合わせたいか」「香りや味わいの好み」を伝え、アドバイスをもらうのが一般的です。
フランス人は価格だけでなく、
- 原料や製法(セパージュ=品種に相当する情報)
- 産地や酒蔵の背景
- 味のプロファイル(甘口・辛口、香りの種類)
- 食事との相性
など、複数の要素を総合的に考慮して選びます。
そのため、日本酒をフランスで広めるには、単なる輸出ではなく「物語と体験」を一緒に届けることが重要なのです。
日本酒の格付けと魅力:「精米歩合」が教えてくれる味わいの秘密
日本酒には、実ははっきりとしたランクがあり、その違いは主に「精米歩合(せいまいぶあい)」と呼ばれる米の削り方、そして製造方法によって決まります。
精米歩合とは、玄米をどれくらい削ったかを示す割合のこと。例えば精米歩合50%なら、玄米を半分以上削って残った中心部分だけを使っているという意味です。数字が小さいほど米を多く削っており、外側に多く含まれる雑味成分を取り除けるため、透明感のあるクリアな味わいと、より香り高い仕上がりになります。
| ランク(説明+ペアリング例) | 名称 | 精米歩合の目安 | 醸造アルコール添加 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ランク1 – 最上級酒(贈答用・特別な日) 高級寿司、白身魚の刺身、祝い膳 |
純米大吟醸 | 50%以下(高精白) | なし | 極めて香り高く繊細で、プレミアム酒の代表格。 |
| ランク2 – 高級酒(特別な日や会食) 刺身盛り合わせ、鯛の塩焼き、フレンチの魚料理 |
大吟醸 | 50%以下 | あり | 純米大吟醸に近いが、醸造アルコール添加で軽やかに仕上がる。 |
| ランク3 – 華やかな香りの食中酒 天ぷら、煮魚、和風パスタ |
純米吟醸 | 60%以下 | なし | 華やかな香りと米の旨味があり、食中酒として人気。 |
| ランク4 – 香り豊かなご褒美酒 焼き魚、塩麹チキン、軽めのチーズ |
吟醸 | 60%以下 | あり | 香り高く軽快で、コストパフォーマンスの良い吟醸タイプ。 |
| ランク5 – こだわり派の日常酒 すき焼き、鰤の照り焼き、味噌田楽 |
特別純米酒 | 60%以下 または 特別な造り | なし | 味わい深く、こだわりのある純米酒。 |
| ランク6 – 軽やかな日常酒 焼き鳥(タレ)、揚げ出し豆腐、鶏の唐揚げ |
特別本醸造酒 | 70%以下 または 特別な造り | あり | すっきりとした味わいで、香りはやや控えめ。 |
| ランク7 – 素朴な味わいの家庭酒 鍋料理、煮物、漬物と一緒に |
純米酒 | 規定なし | なし | 米の旨味を活かした、自然なスタイルの酒。 |
| ランク8 – 日常用の晩酌酒 晩酌の定番、焼き魚定食、和風おつまみ |
本醸造酒 | 70%以下 | あり | 日常使い向けで、すっきりと飲みやすい。 |
プレミアムの頂点「純米大吟醸酒」
最上級に位置づけられるのが純米大吟醸酒です。精米歩合は50%以下、つまり米の半分以上を削るため、米の選別・精米に非常に手間とコストがかかります。
さらに醸造アルコールは一切加えず、米と水と麹(こうじ)だけで仕込むため、素材そのものの旨味と香りが引き立ちます。香りは華やかで、口に含むと繊細かつ奥行きのある味わいが広がります。贈答用や特別な日の乾杯、高級レストランでのペアリングにも最適な、日本酒の「芸術品」とも言える存在です。
米の旨味と香りの調和「純米吟醸酒」
純米吟醸酒は精米歩合60%以下で、米本来の旨味をしっかり感じられながら、吟醸造り特有の華やかな香りも楽しめます。
フレンチやイタリアンといった西洋料理との相性も良く、海外の日本酒ファンからも支持されるカテゴリーです。なお、同じ精米歩合でも醸造アルコールを加えたものは「吟醸酒」と呼ばれ、より軽快でスッキリとした飲みやすさが特徴です。
香り豊かで軽やかな「大吟醸酒」
純米大吟醸と同じく精米歩合50%以下ですが、こちらは少量の醸造アルコールを加えることで、香りを引き立てつつ、より軽やかな口当たりに仕上げられます。
純米大吟醸よりもややカジュアルながら、それでも高級感は十分。料理との組み合わせも幅広く、食前酒としても人気があります。
「純米吟醸」「純米大吟醸」という特別な存在
この流れの中で脚光を浴びたのが、特定名称酒と呼ばれるカテゴリーです。
とくに「純米吟醸酒」や「純米大吟醸酒」は、米の外側を大きく削る「精米歩合」の低さが特徴です。
精米歩合とは、玄米を削った後の重量比率のことで、数字が小さいほど米を多く削っていることを意味します。
米の外側には雑味の原因となるたんぱく質や脂質が多く含まれているため、それらを削ることで、雑味が少なく香り高く透明感のある味わいが生まれます。
フランスでの“日本酒ブーム”を牽引した立役者 -「獺祭」の存在
今日のように、フランス国内の一流レストランや星付きシェフたちが、日本酒をワインリストに堂々と載せるようになったり、日本酒に合わせたオリジナル料理を次々と生み出すようになった先駆けとなったのは、間違いなく「獺祭」の登場です。
山口県の旭酒造が生み出したこの酒は、華やかな果実のような香りと、舌の上で滑らかに広がる口当たりが特徴。日本国内だけでなく、世界中の美食家を魅了し続けています。
ワイン大国で火がついた「獺祭」
フランスといえば、言わずと知れたワイン大国。そんな土地で、米から造る日本酒が人気を得るのは、一見すると難しい挑戦のように思えます。しかし獺祭は、その文化の壁を軽やかに飛び越えました。
その理由は、徹底した品質へのこだわりにあります。獺祭は精米歩合(お米をどれだけ削るかの割合)が非常に高く、たとえば「獺祭23」は米粒を77%も削って、わずかな芯だけを使うという贅沢な造り。この極限まで磨かれた米から生まれる透明感のある香りと、繊細で上品な味わいは、フランスのワイン通の舌にも鮮烈な印象を残しました。
“わかりやすさ”も人気の理由
獺祭の成功を支えたもう一つの大きな要因が、そのわかりやすい商品展開です。フランスで販売されている獺祭は、主に以下のラインナップ。
- Dassai 23(精米歩合23%)…極限まで磨き上げた旭酒造の代表作。華やかな香りと澄んだ旨味。
- Dassai 39(39%)…香りと旨味のバランスが絶妙な、食事と寄り添う一本。
- Dassai 45(45%)…日常の贅沢として楽しめる、ふくよかな味わい。
- Coffret dégustation(3銘柄を少量ずつ楽しめるテイスティングセット)
「Dassai」の後に続く数字は、米をどれだけ削ったかを示す精米歩合のパーセンテージ。潔いほどシンプルな命名で、数字が小さいほど手間をかけた高級品であることが一目でわかります。
一度どれかを試した人は、「23と39、どっちが自分好みかな?」「45も試せば味の違いがもっと分かるかも」と、他の銘柄にも興味を持ちます。まるでワインのヴィンテージを比べるように、獺祭のラインナップを飲み比べる楽しさが広がっていくのです。
見て伝わる“視覚の力”
ボトルデザインは白地に墨文字というシンプルで洗練されたスタイル。名前の横にはっきりと数字が記されているので、日本酒に馴染みのないフランス人でも直感的に「数字が小さいほど高級」というルールを理解できます。
この“視覚的に伝わるラベル”が、日本酒という未知の世界に踏み出す心理的なハードルを下げました。数字のインパクトとシンプルなデザインは、「なんだか面白そうだから、ちょっと試してみようかな」という気持ちを自然に呼び起こします。
従来の日本酒は、ラベルから得られる情報が少なく、初心者には選びにくいものでした。その中で、獺祭はデザインと情報の両面でハードルを下げ、しかもブランドの世界観をしっかりと打ち出すことに成功しました。これは単なるラベルデザインの工夫にとどまらない、戦略的なマーケティングの勝利と言えるでしょう。
パリのシェフたちとの出会い
フランスへの進出にあたって、獺祭の蔵元・桜井社長夫妻は、パリのワインショップやレストランを自ら訪ね、試飲をお願いして回りました。やがて獺祭の魅力に心を奪われたのが、三つ星シェフのジョエル・ロブションやヤニック・アレノといった、世界的な料理人たちでした。
彼らはすぐに獺祭を自らのメニューに取り入れ、フレンチと日本酒という一見異なる文化の“マリアージュ”を提案します。
フォアグラやトリュフといった濃厚なフランス食材にも、獺祭の華やかな香りと切れのある味わいは見事に寄り添い、「フレンチに合う日本酒」という新しいイメージが瞬く間に広がっていきました。
ロブションとのコラボ:パリにおける獺祭の本格進出
ジョエル・ロブション氏とは?
ジョエル・ロブション(Joël Robuchon、1945年4月7日-2018年8月6日)は、フランス料理界の頂点に立った伝説的シェフ。世界最多のミシュラン星を誇り、料理界からは「世紀の料理人」と称されました。
1976年に「フランス最高職人章(Meilleur Ouvrier de France)」を獲得し、1989年には「Chef of the Century(世紀の料理人)」に選出。1981年に独立開業したレストラン「ジャマン(Jamin)」は、わずか3年でミシュラン三つ星を獲得するという快挙を達成します。
その後、「ラトリエ・ドゥ・ジョエル・ロブション(L’Atelier de Joël Robuchon)」を世界各地に展開し、総計32ものミシュランの星を保持するに至りました。
彼の哲学は「素材を最大限に生かす、シンプルかつ高品質な料理」。代表作のポム・ピュレ(じゃがいものピュレ)は、バターをふんだんに使った究極のマッシュポテトとして有名です。また、ゴードン・ラムゼイやエリック・リペールなど、多くの著名シェフに多大な影響を与え、料理界に計り知れない影響を与えました。
柔和ながら厳格な追求心を持ち、「完璧な料理などない」という信念のもと常に高みを目指した彼の仕事は、世界中の美食家から愛され、今もなお料理界に輝く足跡を残しています。
「Dassaï Joël Robuchon」の誕生
2018年4月〜6月、パリ8区フォーブル・サントノレ通りに、旭酒造とロブションが共同で手がけた「Dassaï Joël Robuchon」がオープンしました。
建物は3階構成で、
- 地下:パティスリー
- 1階:ティーサロン兼バー
- 2階:本格ダイニング
という造り。
4月には茶房・バーとパティスリーが営業を開始し、1日約200人が来訪。6月にはフレンチレストラン部門が開店し、グラスやワイングラスで獺祭を提供するペアリング体験が始まりました。
ロブションは「I’m in love with Dassai. It’s the best sake I’ve ever tasted.(私は獺祭に恋している。これまで飲んだ中で最高の日本酒だ)」と語り、日本の酒造りへの敬意を惜しみなく表しました。
メニューと提供スタイル
ここでは獺祭スパークリング50をはじめ、多彩な獺祭銘柄がシャンパングラスやワイングラスで提供されました。料理は黒鱈の味噌漬け、カニの天ぷら、仔羊と春野菜のソテーなど、和と仏が融合した洗練の一皿ばかり。
まるで日本酒がフレンチの中に自然に溶け込み、新しい食文化を生み出していく過程を体験できる場所でした。
残念ながらレストランが開店してたった2ヶ月というタイミングでロブション氏が亡くなり、この店舗はその後閉店してしまいました。しかしその試みは日本酒とフランス料理の関係を大きく前進させた“象徴的な一歩”として、今も語り継がれています。




ヤニック・アレノとの新しい展開:イザカヤスタイルで一流の味を
世界的シェフ、ヤニック・アレノ氏とは?
ヤニック・アレノ(Yannick Alléno、1968年12月16日生まれ)は、フランスを代表するモダンフレンチの巨匠であり、世界でも屈指のミシュラン星保持者です。パリ近郊ピュトーの出身で、15歳という若さで料理の道へ。名門ホテル「ロイヤル・モンソー」や「ル・ムーリス」で修業を積み、2007年には『ル・ムーリス』の料理長として三つ星を獲得しました。
2014年にはパリ・シャンゼリゼに位置する名門「パヴィヨン・ルドワイヤン」を引き継ぎ、『Alléno Paris』として再出発。同年に三つ星を獲得し、さらにアルプスの高級リゾート地クールシュヴェルにある『Le 1947』でも三つ星を獲得。現在では世界18店舗以上を展開しています。彼の代名詞ともいえる革新技術「Extraction®」は、素材の持つ旨味や香りを最大限に引き出す抽出法で、料理界に新たな地平を切り開きました。
「L’IZAKAYA DASSAI」誕生
2024年11月、ヤニック・アレノは獺祭を店名に掲げた居酒屋スタイルのカジュアルなレストラン、『L’IZAKAYA DASSAI by Yannick Alléno』をパリ7区のグルメスポット「Beaupassage」に開業しました。
アレノは30年以上にわたり日本文化、とりわけ日本の食文化に深い関心を寄せてきました。今回の店舗は、その想いを形にしたプロジェクト。日本の大衆酒場「居酒屋」をフレンチの感性で再解釈し、和と洋を軽やかに融合させた空間を作り上げています。高級感がありながらもカジュアルで親しみやすく、誰でもふらっと立ち寄れる雰囲気が魅力です。
店内の雰囲気とメニュー
店内は温かみのある木のインテリアでまとめられ、カウンター式のオープンキッチンからは、料理が出来上がっていく様子と香りがダイレクトに伝わってきます。料理人の手さばきや鉄板の音、揚げ物の香りなど、五感で楽しめるライブ感が魅力です。
メニューは、日本の定番居酒屋メニューをフレンチ流に洗練させたラインナップです。人気のあるメニューを以下に抜粋しました。




- Handrolls(手巻き寿司):巻きたてのライブ感が魅力の軽い一品。
- 刺身盛り(例:鰤の刺身ポン酢) や 牛タタキ(しそ&卵黄コンフィ添え):繊細で華やかな仕上がり。
- カキフライ(揚げ牡蠣)/天ぷら/鶏の唐揚げ:日本の揚げものをフレンチ仕立てで楽しめます
- 海鮮鍋(Pot-au‑feu de la mer/おでん風):あたたかく、心にしみる一品です。
- バーガー・牛テリヤキ(Burger Bœuf Teriyaki):パリのビストロ感と和の融合を象徴する人気メニューです。
- ラーメン(鶏コンソメに半熟卵入り):優しい味わいながら、本格派の仕上がり。
- 豚カツ丼(Katsudon)や親子丼(Oyakodon):豚カツ丼の出汁には昆布や鰹節だけでなく、洋風の香味野菜を加えて深みをプラス:親子丼は鶏と卵の丼を、軽くスモークしたマスと魚卵で再構築する驚きのひと皿。
- 黒鱈の味噌漬け(Black Cod with Miso):味噌と酒に漬け込まれたこだわりの一品。
店舗の基本情報
- 店舗名:
L’IZAKAYA DASSAI by Yannick Alléno(イザカヤ ダッサイ by ヤニック・アレノ) - 所在地:
Beaupassage(ボーパサージュ内)
53–57 Rue de Grenelle, 75007 Paris, France - アクセス:
地下鉄「Rue du Bac」駅が最寄り駅です - 電話番号:01 84 74 21 21
- 公式サイト:https://www.lizakaya-alleno.com/
パリで味わう“日本の酒”の深淵 – Salon du Sakéとは?
フランス・パリで毎年秋に開催される「Salon du Saké(サロン・デュ・サケ)」は、ヨーロッパ最大規模を誇る、日本酒と和の飲料文化の祭典です。
会場には日本酒だけでなく、焼酎、梅酒などの果実酒、緑茶、さらには和菓子や工芸品、観光情報までが一堂に集まり、まるで日本の“味と文化”を丸ごと体験できるショーケースのような空間になります。
2025年の開催概要
今年の開催は2025年10月4日(土)〜6日(月)の3日間。会場はセーヌ川沿い、パリ15区の「New Cap Event Center」。
1,500㎡の広大なフロアに、全国各地の酒蔵や輸入業者が勢ぞろいし、600種類以上の日本酒や関連商品が来場者の目と舌を楽しませます。
昨年は来場者数が約6,000人、出展者はフランスを中心に世界中から50〜60社が参加。まさに日本酒が欧州市場で存在感を増していることを示すイベントです。
試飲だけじゃない、学べるプログラム
Salon du Sakéの魅力は、ただ飲んで味わうだけではありません。
ソムリエや酒ソムリエ、蔵元による講演、マスタークラス、ワークショップなど、学びの場も充実しています。多くは無料で参加でき、人気セッションは事前予約が必要。有料テイスティングでは「和菓子と日本酒のマリアージュ」など、普段なかなか体験できないペアリングの世界を味わえます。
入場方法とチケット
- 一般来場者:土曜・日曜のみ入場可。
- 1日券:25ユーロ
- 2日券:40ユーロ
オンラインまたは当日会場で購入可能。
- 業界関係者(プロ向け):最終日の月曜のみ。名刺や職種証明で入場無料。
パリでは「Sake Weeks」などの関連イベントもありますが、このSalon du Sakéはその中心的存在です。ミシュランシェフとコラボする醸造家や、フランスの酒文化の第一人者など豪華な講師陣が登壇。
スパークリング日本酒をワイングラスで味わったり、純米大吟醸とフレンチチーズをペアリングしたり – 日本酒が“ワインに並ぶ選択肢”として受け入れられつつある現場を体感できます。
日本酒を手に入れるなら – パリのおすすめショップ
パリではここ数年、日本酒を扱う専門店やセレクトショップがじわじわと増えています。観光客だけでなく、地元のフランス人の間でも「家で日本酒を楽しむ」文化が広がっているのです。そんな中、初心者から通まで満足できるおすすめの3店舗をご紹介します。
- Maison du Saké(メゾン・デュ・サケ)
住所:11 rue Tiquetonne, Paris 2区
日本酒ファンなら一度は訪れたい、パリ随一の日本酒専門店。全国各地から厳選した銘柄がずらりと並び、山口の獺祭や山形の十四代など、希少品に出会えることもあります。スタッフは日本酒の知識が豊富で、初心者にも産地や味わいの特徴を丁寧に説明してくれるので、自分の好みに合う一本を安心して選べます。夜は併設のバーで、グラスでの飲み比べも可能。
公式サイト: https://www.lamaisondusake.com - Workshop Issé(ワークショップ・イッセ)
住所:11 rue Saint-Augustin, Paris 2区
和の雰囲気漂うセレクトショップで、日本酒はもちろん、和食材や調味料も充実。店内にはランチタイムに営業する和食レストランも併設され、食事とともに日本酒を楽しめます。また、定期的にテイスティング講座や日本酒セミナーを開催しており、味わい方やペアリングのコツを学びたい方にもおすすめです。
公式サイト: https://www.workshop-isse.fr - Irasshai(イラッシャイ)
住所:40 rue du Louvre, Paris 1区
近代的でおしゃれな内装が特徴のコンセプトストア型ショップ。高級酒から日常使いできる手頃なボトルまで幅広く揃っており、気軽に立ち寄れる雰囲気が魅力です。店内ではワインのように日本酒をカジュアルに試飲でき、ギフト用のラッピングサービスも充実。観光客にも地元の常連にも人気の一軒です。
公式サイト: https://irasshai.co - Wakaze(ワカゼ)
住所:31 rue de la Parcheminerie, 75005 Paris
南フランス・カマルグの米を使った「メイド・イン・フランス日本酒」を手がけ、2022年にはパリ5区に初の居酒屋スタイル店舗をオープン。フランスらしいアプローチで日本酒を“地元の酒”として普及させる試みを行っています。
公式サイト(店舗ページ):
https://www.wakaze-sake.com/pages/restaurant_wakazeparis

日本酒の進出はほんとにすごいね。僕も日本酒は大好きだけど、日本酒が本当の意味で好きになったのはフランスに来てからだと思う。日本にいた頃は蕎麦が好きで、蕎麦屋で板わさなどをつまみながら、まだ明るい時間から飲むことが大好きだった。ただ日本酒に関しては「冷」か「熱燗」かを選ぶくらいで、銘柄まで気にしたことはなかったな。お店の人も細かい説明なんてしないし、銘柄などを聞くのは、なぜかおこがましい気がして遠慮していた気がする、今思うと変だけど。
だから10数年前に、パリのオデオン広場そばにある「La Maison du Whisky Odéon」で獺祭の試飲会が行われると聞いて「日本酒なんて珍しい」と行ってみたのが、日本酒との本当の出会いだったと思う。獺祭の社長ご夫妻が、来場者一人ひとりの細かな質問にとても丁寧に対応されていて、中には「こんなことまで社長に聞く?」というような質問もあり、「通訳さんがいるとはいえ、大変ではないですか?」とお聞きしたら、「日本の試飲会では、こんなにたくさんの質問は出ませんし、日本人では思いつかないような質問も多くて勉強になります。」と笑顔で仰られていて、獺祭のブランドオーナーというだけでなく、日本酒全体のアンバサダーという感じだった。確かに日本では、ワインのように香りや味わいを花や果物にたとえたり、料理によって銘柄を変えて飲むことはあまりしないよね。その点、獺祭はフルーティで後味がすっきりしているので、香りや味をワインのように表現しやすく、和食はもちろん、フランスの前菜とも相性抜群だ。特にフランス人にとっては、全く新しいワインを飲んでいるような体験で、初めて接する日本酒として最適だと思う。実際、この試飲会に一緒に行ったフランス人の友人は、日本料理店で中国の白酒をSAKEと言われて飲んで以来、日本酒に苦手意識を持っていたんだけど、獺祭を一口飲んだ瞬間にその印象が覆り、日本酒が大好きになっちゃった。今ではさまざまな日本酒を試しているものの、一番のお気に入りは今も獺祭なんだそうだ。
僕もたくさん日本酒は飲んできたけど、獺祭を初めて飲んだ時には、「コクのある白ワインを飲んでいるみたいだ」と驚いた。日本酒としては甘味が強いほうだと思うけど、華やかでキリッとした白ワインに旨味を足したみたいな不思議な美味しさだった。確かに前菜からフロマージュまで、一緒に食べるものの美味しさを更に開いてくれるようで、まさにマリアージュだ、と思ったな。
試飲会には料理関係者も多く、料理と日本酒のマリアージュ談義で盛り上がっていたから、「これならフランスでも獺祭が飲めるお店が増えるかも」と期待していたら、名だたるフランス料理のシェフたちが次々と獺祭とのコラボやレストランをオープンすることになり、期待以上にフランスに浸透していた。特に「Dassaï Joël Robuchon」には驚いた。内装も料理も全てが獺祭を体現していて、こんなに格好のいいアルコール、他にある?とまで思わせるような、あっと驚く空間だった。
ジョエル・ロブション氏が亡くなったときは、フランス中で連日特集が組まれるほどの大ニュースだったんだ。オープンしたばかりのDassaïはどうなるのだろうとハラハラしていたけど、やっぱり閉店してしまった。彼は獺祭に特別な想いを持っていたから、他の人では彼の哲学を引き継げないと判断したのではないかな。ほんとうに残念でならない。
フランスを代表するシェフであるとともに、料理番組も持ち、料理の楽しさをユーモアを込めて丁寧に教えていたから、フランス中の主婦たちが、彼の生徒たちだった。彼がフランス料理に果たした役割は計り知れない。
しかし、それで獺祭とミシュランシェフとのコラボが終わったわけではなかった。2025年には、合計16のミシュラン星を持ち、東京やドバイなどでも活躍するヤニック・アレノ氏が「L’Izakaya Dassai by Yannick Alléno」をオープン。こちらはよりカジュアルなスタイルで、居酒屋の定番メニューを世界的シェフがアレンジするとこうなるのか!という驚きも楽しめる。
コースは69ユーロ(約11,800円)で、ボリュームは軽めだけどスターシェフの居酒屋としては手頃だと思う。ただ、残念なのはグラスで飲める獺祭が2種類しかなく、価格も高めなこと。8cL(80mL)のDASSAI DEX 45が16ユーロ(約2,700円)、DASSAI 39が20ユーロ(約3,400円)。獺祭とフランス版居酒屋料理のマリアージュが目的だから、食事やデザートそれぞれに合わせて、合わせるお酒の種類を変えたいよね。そのためにはグラスで頼めるのが2種類というのは少ないと思うし、いくらパリでもグラスで3千円もしたら、気軽に何杯も飲めるような金額ではない。ショップではDassai 45は、720mlでだいたい38ユーロ(約6,500円)ぐらいで、パリで買える日本酒としては、それほど高いわけではないんだ。レストラン価格になってしまうのは仕方ないとしても、獺祭を気軽に試してもらう店舗として(それこそが居酒屋の役割だと思うんだけど)、もう少し原価に近い値段で出してもらいたいな。高級なお酒というイメージが強くなりすぎると、若い世代が日本酒から距離を置いてしまいそうで心配だ。
とはいえ、獺祭の名前が著名シェフのレストランに冠されるのは快挙だし、日本の酒造技術が世界に認められた証だ。
日本では今、米の生産減少が深刻で、日本酒業界にも影響を与えているけど、せっかく海外で日本酒の波が来てるのに、このまま勢いが落ちてしまうのは残念だ。せっかく海外で勢いがついた日本酒の波が、勢いを落としてしまうのは悲しい。でもフランスやイタリアでも日本米に近い品種は栽培可能だから、Wakazeのように現地米を使い、日本の精米技術を導入すれば、日本の銘酒に近い品質の酒を造ることも夢ではないかもしれない。技術流出には注意する必要はあるけれども。
米の問題と海外での日本酒人気の高まりが同時期に重なったのは痛手だけど、日本の農業技術なら酷暑にも耐える品種改良で必ず乗り越えられるはず。日本政府も増産を決めた以上、責任を持って継続することを(担当大臣が変わっても政策をコロコロ変更したりしないように)、海外からも見守っているよ。